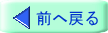
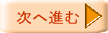
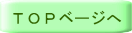
(3)環境基本法における環境教育
1980年代後半に入ると、環境教育の必要性についての認識がますます高まります。
この流れを受け、環境庁では1986年、環境教育のあり方についての基本姿勢を整理する「環境教育懇談会」を設置しました。懇談会では1988年3月に「みんなで築くよりよい環境を求めて」という報告書をとりまとめ、その中では、次のような課題が示されています。
1.情報、教材等の充実
2.環境教育活動のための拠点の整備
3.民間活動の支援体制の整備・充実、指導者の育成
4.ネットワークの形成・整備
1993年になると環境基本法が成立しました。環境基本法では、「今日の環境問題を解決するためには、経済社会システムやライフスタイルを環境への負荷の少ないものとへと変革していく必要がある」という考え方にたち、多様な施策を講ずることを規定しました。環境教育・環境学習の振興については、第25条で次の様に規定し、環境教育・環境学習の重要性が法制上、初めて位置づけられました。
第25条
「国は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により事業者及び国民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。」
環境基本法に基づき作成された環境基本計画(1994年)では、「持続可能な生活様式や経済システムの実現のために環境保全に関する教育及び学習を推進すること」を定めています。計画の中では、学校における環境教育の重要性、社会教育その他、多様な場における環境教育・環境学習、広報の充実について述べられています。
特に社会教育においては、「学習拠点の整備、学習機会の提供、人材の育成・確保、教材・手法の提供を推進すること」を盛り込んでいます。