丂儗僢僪僨乕僞僽僢僋偲偼丆愨柵偺偍偦傟偺偁傞栰惗惗暔傪儕僗僩傾僢僾偟丆偦傟偧傟偺庬偵偮偄偰偺惗懅丒惗堢忬嫷傗愨柵偺婋尟搙偵偮偄偰夝愢偟偨曬崘彂偱偁傞丏偦偺偼偠傑傝偼IUCN 乮崙嵺帺慠曐岇楢崌乯偐傜1966 擭偵弌斉偝傟偨悽奅儗儀儖偱偺曬崘彂偩偑丆偦偺屻奺崙偱弴師弌斉偝傟丆擔杮偱傕娐嫬徣乮媽娐嫬挕乯摍偵傛傝丆崙撪偺栰惗惗暔偵偮偄偰傑偲傔偨傕偺偑姧峴偝傟偰偄傞丏偙傟傜偺曬崘彂偼奺庬奐敪峴堊偺幚巤摍偵嵺偟丆帺慠娐嫬偺曐慡傗栰惗惗暔偺曐岇偵攝椂偡傞偨傔偺婎慴忣曬偲偟偰懡曽柺偱妶梡偝傟偰偄傞丏偟偐偟側偑傜丆杮棃丆栰惗惗暔偺暘晍忬嫷傗惗懅丒惗堢枾搙偼抧堟偵傛偭偰堎側傞偨傔丆慡崙揑偵偼愨柵偺偍偦傟偑掅偔偲傕抧堟揑偵偼懚懕偑婋傇傑傟傞偲偄偆庬傕懚嵼偡傞丏偦偙偱昁梫偲側傞偺偑丆懳徾抧堟傪峣傝崬傫偩抧曽斉儗僢僪僨乕僞僽僢僋偱偁傝丆偡偱偵懡偔偺搒摴晎導偵偍偄偰偦偺嶌惉偑専摙丒幚巤偝傟偰偄傞偲偙傠偱偁傞丏
丂杮彂偼丆暉堜導偵惗懅偡傞栰惗怉暔傪懳徾偵丆嵟怴偺抦尒傪傕偲偵偦傟偧傟偺庬偺尰帪揰偱偺愨柵偺偍偦傟傪昡壙偟偨暉堜導斉偺儗僢僪僨乕僞僽僢僋偱偁傝丆崱屻丆杮導偵偍偗傞惗暔懡條惈曐慡傊偺庢慻傒偺偨傔偺婎慴帒椏偲偟偰妶梡偝傟傞偙偲傪栚揑偵嶌惉偝傟偨傕偺偱偁傞丏
(2)丂挷嵏丒専摙懱惂
丂暉堜導偺惗暔懡條惈偵娭偡傞挷嵏偼丆暉堜導帺慠娐嫬曐慡忦椺偵婎偯偒1973 擭偐傜掕婜揑偵暉堜導帺慠娐嫬曐慡挷嵏尋媶夛偵傛偭偰幚巤偝傟偰偒偨丏摨尋媶夛偼丆導撪偺戝妛丆彫拞崅峑偺嫵怑堳偍傛傃柉娫偺尋媶幰摍偱峔惉偝傟偨抍懱偱偁傝丆嵟嬤偱偼暯惉4 擭搙偐傜暯惉10 擭搙偵偐偗偰丆導撪慡堟傪捁廱丆崺拵丆棨悈惗暔丆椉惗唳拵椶丆棨嶻奓椶丆抧宍抧幙丆怉惗丆宨娤偺奺暘栰偱挷嵏傪幚巤偟偰偄傞丏傑偨丆偦偺惉壥偼丆乽暉堜導偺偡偖傟偨帺慠乿丆乽暉堜導崺拵栚榐乿丆乽暉堜導偺棨悈惗暔乿丆乽暉堜導偺椉惗椶丒唳拵椶丒棨嶻奓椶栚榐乿摍偺曬崘彂偵傑偲傔傜傟傞偲偲傕偵丆杮導偺儂乕儉儁乕僕傪捠偟偰峀偔堦斒偵岞奐偝傟偰偄傞丏
丂杮彂傪嶌惉偡傞偵偁偨偭偰丆摨尋媶夛偺夛挿傪偼偠傔偲偡傞導撪奜偺愱栧壠偵傛傞乽暉堜導斉儗僢僪僨乕僞僽僢僋嶌惉専摙埾堳夛乿傪愝抲偟丆嶌惉曽恓摍偵偮偄偰専摙傪峴偭偨丏摨尋媶夛偼丆偦偺曽恓偵婎偯偒丆偙傟傑偱偵廤愊偟偨忣曬傪婎慴偲偟丆昁梫偵墳偠偰曗姰挷嵏傪暲峴偝偣側偑傜暯惉11 擭搙偐傜暯惉13 擭搙傑偱偺3擭娫偱摦暔曇丆暯惉13擭搙偐傜暯惉15擭搙傑偱偺3擭娫偱摦暔曇偺嬶懱揑側曇廤嶌嬈傪恑傔偨丏
埾丂堳乮傾儖僼傽儀僢僩弴乯
暉堜導斉儗僢僪僨乕僞僽僢僋嶌惉専摙埾堳夛
| 丂丂埾丂堳丂柤 | 強丂丂丂懏乮愝抲摉帪乯 |
| 丂堬丂忛丂峃丂峅 | (嵿)帺慠娐嫬尋媶僙儞僞乕丂庡擟僐乕僨傿僱乕僞乕 |
| 丂彫丂椦丂娹 | 暉堜導帺慠娐嫬曐慡怰媍夛夛挿 |
| 丂嵅乆帯丂姲丂擵 | 暉堜戝妛嫵堢抧堟壢妛晹嫵庼乮暉堜導帺慠娐嫬曐慡挷嵏尋媶夛挿乯 |
| 丂怉丂揷丂柧丂峗 | 娐嫬挕帺慠曐岇嬊栰惗惗暔壽栰惗惗暔愱栧姱 |
| 丂墶丂嶳丂弐丂堦 | 暉堜戝妛嫵堢抧堟壢妛晹彆嫵庼 |
暉堜導帺慠娐嫬曐慡挷嵏尋媶夛
婇夋埾堳夛
| 晹丂夛 | 巵丂柤 | 強丂懏 |
| 丂捁廱晹夛 | 丂椦丂丂晲丂梇 | 丂擔杮捁椶曐岇楢柨棟帠 |
| 丂椉惗丒唳拵椶晹夛 | 丂挿扟愳丂娹 | 丂晲惗巗晲惗搶彫妛峑挿 |
| 丂棨悈惗暔晹夛 | 丂壛丂摗丂暥丂抝 | 丂恗垽彈巕抁婜戝妛嫵庼 |
| 丂崺拵晹夛 | 丂嵅乆帯丂姲丂擵 | 丂暉堜導帺慠娐嫬曐慡挷嵏尋媶夛挿 |
| 丂怉暔晹夛 | 丂墶丂嶳丂弐丂堦 | 丂暉堜戝妛嫵堢抧堟壢妛晹彆嫵庼 |
怉暔晹夛
| 巵丂丂柤 | 強丂丂懏 | 旛丂丂峫 |
| 丂埨丂払丂丂丂桿 丂暉丂塱丂媑丂岶 丂暯丂嶳丂垷婓巕 丂愇丂杮丂徍丂巌 丂杒丂愳丂攷丂惓 丂彫丂椦丂懃丂晇 丂崟丂揷丂柧丂曚 丂徏丂懞丂宧丂擇 丂惸丂摗丂姲丂徍 丂嵵丂摗丂朏丂晇 丂郪丂嶈丂岶丂栫 丂懡丂揷丂夒丂廩 丂忋丂嶁丂惓丂晇 丂庒丂悪丂岶丂惗 丂搉丂曈丂掕丂楬 丂墶丂嶳丂弐丂堦 |
丂暉堜棨悈惗暔尋媶夛 丂暉堜導棫椾撿惣梴岇妛峑 丂暉堜導帺慠曐岇僙儞僞乕 丂尦暉堜導棫戝栰崅摍妛峑 丂尦彑嶳巗棫峳搚彫妛峑 丂尦彑嶳巗棫彑嶳撿晹拞妛峑 丂暉堜導棫彑嶳撿崅摍妛峑 丂尦彑嶳忛攷暔娰 丂尦暉堜導棫嶪峕崅摍妛峑 丂擔杮僔僟偺夛夛堳 丂暉堜導棫扥惗崅摍妛峑 丂暉堜導帺慠曐岇壽 丂尦暉堜導棫庒嫹崅摍妛峑 丂暉堜憤崌怉暔墍 丂暉堜巗帺慠巎攷暔娰 丂暉堜戝妛嫵堢抧堟壢妛晹 |
丂 丂 丂 丂娔廋幰 丂 丂 丂 丂 丂 丂 丂 丂 丂 丂娔廋幰 丂娔廋幰 丂晹夛挿 |
挷嵏丒曇廤嫤椡乮傾儖僼傽儀僢僩弴乯
- 愺嵢惓巕丂暉堜巗帺慠巎攷暔娰丂暉堜憤崌怉暔墍丂恄揷旤撧巕丂愳撪堦寷丂嶰尨妛丂娭壀桾柧丂幠揷椇弐丂敧栘寬帰丂媑懞梞巕
幨恀採嫙乮傾儖僼傽儀僢僩弴乯
- 惵栘恑丂埨払桿丂墊杮攷擵丂暉堜導帺慠曐岇僙儞僞乕丂暉堜導怉暔尋媶夛丂暉塱媑岶丂愇杮徍巌丂彫椦懃晇丂徏杮弤丂彫愳寷彶丂庒悪岶惗
- 偙偺懠丆暉堜導怉暔恾娪偐傜懡偔偺幨恀傪揮嵹偟偨丅
丂 - 偙偺懠丆暉堜導怉暔恾娪偐傜懡偔偺幨恀傪揮嵹偟偨丅
(3)丂昡壙偺婎弨
丂昡壙婎弨偼丆娐嫬徣偺僇僥僑儕乕偺掕惈揑梫審乮暿昞嶲徠乯傪婎杮偲偟側偑傜丆暉堜導偑尰帪揰偱桳偡傞昡壙偺偨傔偺忣曬傪峫椂偟偰昞偺偲偍傝掕傔偨丏
丂傑偨丆屄乆偺庬偺昡壙偵偁偨偭偰偼丆杮彂偵宖嵹偟偨庬偑娐嫬徣偺儗僢僪僨乕僞僽僢僋偵宖嵹偝傟偰偄傞応崌丆尨懃偲偟偰偦偺儔儞僋傪娐嫬徣偺僇僥僑儕乕埲忋偲偟偨丏
| |
丂夁嫀偵暉堜導偵惗懅偟偨偙偲偑妋擣偝傟偰偄傞偑丆暉堜導偵偍偄偰栰惗偱偼偡偱偵愨柵偟偨偲峫偊傜傟傞庬
| |
| |
丂師偺偄偢傟偐偵奩摉偡傞庬
| |
| |
丂師偺偄偢傟偐偵奩摉偡傞庬
| |
| |
| |
|
乮暿昞乯娐嫬徣偺僇僥僑儕乕乮娐嫬挕丆1997乯
(4)丂慖掕寢壥
丂嘆僇僥僑儕乕暿慖掕庬悢
| 丂 | 愨丂柵 | 愨柵婋湝 嘥椶 |
愨柵婋湝 嘦椶 |
弨愨柵婋湝 | 梫拲栚 | 憤丂寁 | |
| 堐 娗 懇 怉 暔 |
僔僟怉暔 | 1 | 31 | 13 | 10 | 9 | 64 |
| 庬巕怉暔 | 12 | 128 | 117 | 66 | 71 | 394 | |
| 彫丂丂寁 | 13 | 159 | 130 | 76 | 80 | 458 | |
| 扺悈憯椶 | 丂 | 12 | 丂 | 3 | 19 | 34 | |
| 崌丂丂寁 | 13 | 171 | 130 | 79 | 99 | 492 | |
| 丂 | 愨丂柵 | 愨柵婋湝 嘥A椶 |
愨柵婋湝 嘥俛椶 |
愨柵婋湝 嘦椶 |
弨愨柵婋湝 | 憤丂寁 | |
| 堐 娗 懇 怉 暔 |
僔僟怉暔 | 丂 | 丂 | 4 | 5 | 丂 | 9 |
| 庬巕怉暔 | 1 | 6 | 27 | 58 | 12 | 104 | |
| 彫丂丂丂寁 | 1 | 6 | 31 | 63 | 12 | 113 | |
| 扺悈憯椶 | 丂 | 12 | 丂 | 3 | 15 | ||
| 崌丂丂丂寁 | 1 | 49 | 63 | 15 | 128 | ||
- 丂嘇慖掕庬堦棗昞
丂- 丂丂丒娐嫬徣僇僥僑儕乕
- 乽夵掶丒擔杮偺愨柵偺偍偦傟偺偁傞栰惗惗暔乿乮嵿抍朄恖帺慠娐嫬尋媶僙儞僞乕2000乯偵婎偯偄偰婰嵹偟偨丅
- 乵HTML僼傽僀儖丆110KB乶
丂
| ||||||||||
| 仠慖掕棟桼 | 惗堢抧偺悢偲屄懱悢偍傛傃偦傟傜偺尭彮孹岦丄婛抦偺惗堢抧偵偍偗傞惗堢忬嫷摍偵偮偄偰婰嵹偟偰偁傞丅 | 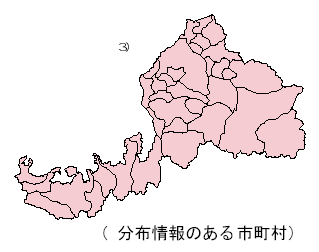 | ||||||||
| 仠惗堢娐嫬 | 摉奩庬偺惗堢娐嫬偵偮偄偰婰嵹偟偰偁傞丅 | |||||||||
| 仠婋尟梫場 | 摉奩庬偺懚懕偵偲偭偰嫼埿偲側偭偰偄傞梫場偱丄尰嵼傑偨偼夁嫀偵摥偄偨傕偺丄側傜 傃偵嬤偄彨棃偵梊應偝傟傞傕偺傪楍婰偟偰偁傞丅 | |||||||||
| 仠暘晍堟 |
| |||||||||
| ||||||||||
![[暉堜導偺巗挰懞埵抲恾]](plantmap/fukuimap.gif)
|
[愭摢儁乕僕] [師偺儁乕僕]
Copyright(C)2004 暉堜導帺慠曐岇壽
