環境ふくい推進協議会の情報紙
みんなのかんきょう
第41号 平成17年1月発行
 |
【主な内容】 /// ふるさとの環境自慢 /// 和泉村 「油坂峠の句碑・蝶の水」 /// 特 集 /// 森林と人との共生 /// 私達の活動紹介 /// |
| 表紙写真 「マガン」 撮影/松村俊幸 |
環境ふくい推進協議会の情報紙
第41号 平成17年1月発行
 |
【主な内容】 /// ふるさとの環境自慢 /// 和泉村 「油坂峠の句碑・蝶の水」 /// 特 集 /// 森林と人との共生 /// 私達の活動紹介 /// |
| 表紙写真 「マガン」 撮影/松村俊幸 |
明治の初め頃までは、越前から美濃に入るには現在の国道はなく、穴馬街道、美濃街道が主要道路であった。これらの街道は共に難所が多く、決して安全とは言えなかった。
荒島岳の麓を通る穴馬街道には落石、崩壊、転落など命がけの九頭竜峡谷があり、一方、美濃街道には越前への入口に、句碑に刻されている難所、油坂峠があった。
 |
| 湧水地から湧き出る清水 |
和泉村の中心、朝日から車で約三十分。中部縦貫道油坂料金所の手前を左折して国道を進むと、油坂トンネルの手前左側に、「蝶の水」の案内看板がある。その山際に穴馬街道跡が歴然と認められる。これを辿りながら上ること約十分、靴底に湿っぽさを感じ始めるとすぐに、当時、峠越えの旅人や牛馬の癒しの場となった平らな広場に出る。その中央あたりに句碑がある。すぐ手前の窪んだ所から清水が静かに湧いているのが分かる。蝶の水である。
白鳥町側から上るとき、脂汗が流れたことからこの名が付いたという油坂峠は標高八百メートル。越前と美濃を跨ぐ難所で水飲み場がなかった。
白鳥町の豪商、皎月亭兎囿(こうげつていとゆう)の号を持つ俳人 原左次郎(はらさじろう)は、旅人や牛馬の苦しむ様子を見かねて、家族を引き連れ数日間山に隠って、至る所を堀ったが水が出なかった。それでも神仏の加護を信じながら岩を起こし、岩壁を破って堀ったところ、念願の清水が湧き出た。
 |
| 句碑 |
その歓喜の叫びに、不思議にも数十頭の蝶がどこからともなく現れて舞い、そして飛び去ったという。これが「蝶の水」の謂れである。
広場の中央に鎮座する句碑の正面には、
『峰高う 涌は 恵みの 清水かな』
山本友左坊(やまもとゆうさぼう)
向かって左側面から裏面には、原左次郎が水を探し当てた経緯が刻されている。
また、右側面には穴馬の俳人 一蹄(いってい)の名、そして
『捜し得た 峰の清水や 常ならず』
文政四辛巳七月日
施主 原左次郎正勝
とある。
ところで、この現在の句碑は本物ではない。
誠に残念なことに、平成の初めに紛失したのである。種々手を尽くしたが戻らなかったため、当時の村長 池尾長久(いけおたけひさ)氏が村内の有志に呼びかけて平成十二年五月に復元されたものである。
復元するに当たっては、兎囿の子孫である白鳥町現住 原元文氏(酒造場)の賛同、芭蕉美濃派宗匠三十九代 國島十雨(くにじまじゅうう)氏(岐阜市)の復刻許可、山林所有者 田中光夫氏(各務原市)の承諾など、多くの方々の協力のもとに完成した。
また、白鳥町では原元文氏の呼びかけで、平成十三年、文化財保護協会が道の整備や文化財保護柱を建てるなど、その保全に努められている。
| 国道沿いの案内 |
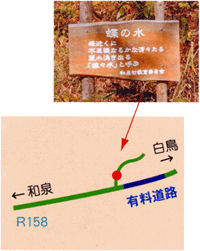 |
油坂峠の句碑は、歴史上誠に意義深いものがある。
青葉の笛伝説の源義平や三日天下の明智光秀が、そして俳諧美濃派の流れを汲む穴馬郷の布仙(ふせん)や一蹄などが脂汗を流した峠であり、そして、この峠を下って流れる「蝶の水」は、明らかに九頭竜の源流となっている。
今、『自然と愛とエネルギー、九頭竜源流の郷』をキャッチフレーズに、住んでよし、訪ねてよしの文化の香り高い学びの郷づくりを目ざす本村にとって、実に示唆されることの多い、大きな存在と考える。
(和泉村教育長 洞口幸夫)
●ふるさとの環境自慢募集中!
みなさんの故郷自慢で一ページをかざりませんか。千字程度の原稿に地図・写真を添付して応募してください。場所の紹介だけでも結構です。 採用された方には記念品をお送りします。
福井県は森林資源などの自然が豊富にあるという恵まれた環境にあることから、わたしたち県民は、そのことが当たり前のように感じられてしまい、森林と関わり合うことや、森林からのさまざまな恩恵を受けていることを忘れがちになっているように思われます。
しかし、近年、福井豪雨災害などの異常気象による自然災害、クマやイノシシなどの出没による人的被害や農作物への被害が増加していることなどから、森林の重要性やその管理のあり方など自然環境への意識が一層高まっています。
このような今こそ、わたしたちは、森林が現在の姿に至った経緯、森林の働きの重要性を再認識し、森林に親しみながら、森林と人との共生を考えることや、森林のボランティア活動など具体的な行動をしていくことが大切であると考えます。
そこで、今回、みなさまの行動のきっかけになればと思い、森林の現状や森林の重要な働き、県の施策について紹介いたします。
古くから人は、森林から、生活に必要な量の木を伐って利用してきましたが、必要とする量が適度であったため、森林が再生するのに支障はありませんでした。
しかし、戦中、戦後には、各種資材や燃料などに利用するための木材が大量に必要になったため、森林が過剰に伐採されました。このため、多くの裸山が見られるようになり、洪水などの自然災害も多く発生しました。
その後、この荒廃した森林の復興と、高度経済成長期における大きな木材需要に応えるため、伐採された跡地や薪炭林などを生産林に変える積極的な造林が行われ、現在の緑豊かな森林の姿となりました。
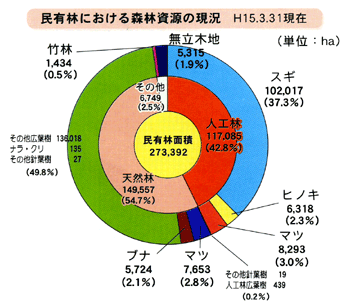 |
福井県の森林面積は313千haあり、県の総土地面積の75%を占めています。これは全国平均67%を上回っており、このうち、国が所有する森林である国有林が39千ha、個人や会社などが所有する民有林が274千haとなっています。
民有林の内訳を見ますと、人工林が117千ha(43%)、天然林が150千ha(55%)、竹林などが7千ha(2%)となっています。
森林には、住宅建設などに使う木材の供給のほか、雨水を地中へ浸透させ、水をストックするという水源かん養、土砂の流出・崩壊の防止や保健休養の場の提供などの働きがあり、わたしたちの生活に多くの恩恵をもたらしています。また最近では、地球温暖化防止の観点から、二酸化炭素の吸収源としての働きが期待されています。
これらの森林の働きを貨幣換算すると、1年間に全国では約70兆円、本県では約1兆1千億円になると試算されています。
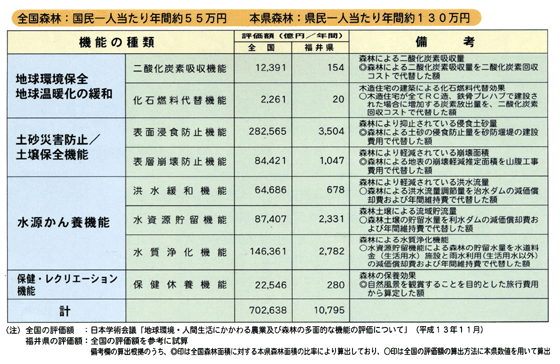 |
森林のさまざまな働きの確保を目指し、効率的・効果的な森林の整備を推進するため、県内の森林を、重視すべき機能に応じて、「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」の3つに区分し、それぞれの望ましい姿を踏まえ、区分に応じた適切な整備・保全を推進しています。
具体的には、針葉樹と広葉樹の混交林化、森林の裸地化を防ぐための複層林化(注)などを進める森林整備事業や、山地被害防止などの機能の向上や維持を図るための治山事業、林業生産の低コスト化や森林管理の基盤としての林道開設等の路網整備などを実施しています。
(注)複層林とは、樹齢、樹高の異なる樹木により構成された森林をいいます。
| 「資源の循環利用林」 | 「森林と人との共生林」 | 「水土保全林」 |
|---|---|---|
 |
 |
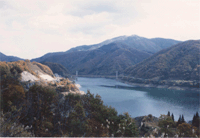 |
| 木材などの効率的・持続的 な生産を重視する森林整備 |
森林生態系や生活環境の 保全、森林空間の適切な 利用を重視した森林整備 |
水源かん養、山地災害の防止 などを重視する森林整備 |
| 整備面積 71,096ha(26%) | 整備面積 11,033ha(4%) | 整備面積 191,382ha(70%) |
|
|
今日、木材の代替品が増加し木製品が日常生活の中から姿を消すなど、これまでの長い歴史の中で培われてきた森林や木材と人との関係が希薄になりつつあります。その一方で、森林への多様なニーズや余暇時間の増大、ボランティア活動への理解や環境問題の関心が高まる中で、市民グループやボランティアによる森林体験活動や森林整備の活動がより活発化する傾向にあります。
そこで、県では春季と秋季に実施している「緑の募金」活動や「緑化大会」などを通じて、森林づくりの普及啓発を行っています。
また、緑を愛し守り育てることを学ぶため、小学生による緑化活動を行うグループとして「緑の少年団」を育成しており、この団員が参加する森林づくり学習の場の提供や活動等に対する支援を行っています。
さらに、市民グループ等のボランティア活動による森林づくりなど、県民自らが森林の整備や保全に参加出来るよう、参加希望者と受け入れ者をつなぐ森林づくり情報ネットワーク体制の整備を進めるとともに、県内の里山7地域において、モデル林を設定し、市民参加型の森林づくりを実施しています。
森林は、先人たちの営々とした森林整備の結果、戦後の荒廃した裸山の状態から立ち直り、今では豊かな森林になりました。
しかし、木材価格が下がったため森林所有者の林業経営に対する意欲が低下する一方、外国産木材の輸入が増え、その結果、ますます国内の木材が利用されず、利用されないため森林が荒廃するという悪い循環の状況にあります。
一方、世界の各地では多くの森林が伐採され砂漠化が進むなど、地球環境の悪化が問題となっていますが、日本では豊かな森林に恵まれており、この森林を後世に引き継いでいくことが大切です。
木は、日本文化を育んできた我が国の国土に合った自然素材で、木目の心地良さ、暖かさ、やわらかさ、調湿作用など、多様な優れた特性を持っています。この木材を利用するということは、地域産業の活性化を促すとともに、健全な森林整備が図られ、森林の持つ様々な働きの発揮につながります。
県では、現在、成長段階にある多くの森林について、健全な森林の育成や優良な木材の生産のために必要な間伐や抜き伐りなどを積極的に取り組んでいます。
また、「木を伐って、木を使う」という木材の流れの循環を良くするため、木を公共施設の木造・木質化や公共土木工事などへの利用を推進するとともに、乾燥材等の品質・性能の明確な製品の安定供給を図ることにより住宅での利用を支援しています。
|
|||||||||
|
|||||||||
環境と調和した持続可能な循環型社会を目指そうとしている今日、さまざまな恩恵をもたらす森林の整備・保全は重要な課題となっています。
森林の現状や県の取組みなどについて述べてきましたが、最も大切なことは、県民のみなさまが多様な公益的機能を発揮する環境財としての森林の重要性、それに「木を伐って、木を使う」という林業としての重要性について、今一度、真剣に思いをめぐらしていただくことだと考えます。
人が森林生態系の一員として生活してきたことを思い出し、今後、一人ひとりが何をどのようにすれば良いかを考え、一人ひとりができることを実践しながら、県民全体で福井の森林に親しみ、守り育て、新たな「森林と人との共生」の関係をつくりだしていきましょう。
(福井県農林水産部森づくり課)
福井県森づくり課ホームページ
http://info.pref.fukui.jp/mori/contents.html
○森林づくりボランティア、森林フィールドの提供の募集
○県民参加型の森林づくりへの参加者の募集
○森林・林業の解説や野外体験学習等の指導員の募集
○その他の森林・林業・木材産業に関する県の施策の紹介
ふくい森林づくり情報ネット「うららの森」
http://www.fukui-green.or.jp/uraranomori/
○森林づくりボランティア、森林フィールドの提供の募集
○里山や森林づくりに関するイベント情報
☆地域・組合員参加の環境活動☆
福井県民生協は2000年にISO14001を取得し、環境リサイクルの活動を積極的に進めてきました。昨年は温暖化防止自主行動計画を作成し、地球環境保全の継続的改善に取り組んでいます。
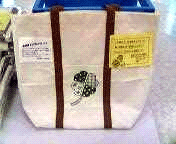 |
【オリジナルマイバックを作成】
生協のお店ハーツでは、買物袋持参率60%と県内でもダントツの持参率を誇っていますが、さらに持参率を上げるために組合員のデザインを採用したオリジナルマイバックを県内の福祉施設「ひまわり作業所」と協力して作りました。完成した買物袋はリサイクルの日(10月20日)に店頭で販売しました!次の目標は買物袋持参率70%です!
【ハーツ環境教室の実施】
 |
ハーツ各店を、食や環境の生きた教材として考え、地域の小中学校の受入れを行っています。リサイクルや環境保全活動などの学習や見学の場として広く開放しています。昨年も12校351人の小中学生の受入れをさせて頂きました。見て!聞いて!体験して!学ぶことのできるハーツ教室は大好評です。
他にも県民生協は、昨年、福井市のモデル事業でプラ容器・紙製容器の店頭回収に取り組んできました。
これからも地域を第一に考えた環境活動に積極的に取り組んでいきます。
県民生協ネットワーク推進部 TEL 0776−22−0808
 |
蓮如の里として知られる、吉崎。私たちの吉崎小学校は北潟湖の湖畔に面している小学校です。
吉崎小学校では、平成12年度から毎年、5・6年生の総合的な学習の時間に北潟湖の水質調査を行っています。調査内容は、気温・水温・透視度の測定、パックテストによる水の成分調査です。また、毎年のデータの比較検証などもしています。その活動が認められて、福井県小中学生科学アカデミー賞(福井新聞社主催)や地球ピカピカ大賞(日本石鹸洗剤工業会主催)といった素晴らしい賞も頂きました。
 |
子どもたちが水質調査を通して驚いたことがありました。それは、北潟湖周辺のゴミの量です。コンビニの袋や空き缶、ペットボトルはもちろん、釣り糸や魚釣りのえさのパック…なんと家電まで捨てられていたのです。そこで、今年は学校と保護者が一丸となって北潟湖畔のごみ拾い活動をしました。私たちのふるさとがこんなにも汚れているということに大人も子どもも驚きました。そして、このままではいけないと強く感じました。
子どもたちが大人になる十年後、二十年後。その未来に、歴史ある美しい吉崎を保っていきたいと思います。そして、子どもたちには、このふるさとを愛し、守っていく心を養っていってもらいたいと願いながら、活動を続けていきたいと思います。
あわら市吉崎小学校 教諭 長谷川忍
特集を読んで、こんなにも食べ残しによる食品廃棄物が多いとは知らず、とても驚きました。同時に家庭から出るゴミのリサイクルが1%と非常に低いと知り、このままではいけないと痛感しました。
(鯖江市 主婦 女性)
今年の夏は孫たちと省エネ作戦として、電気量を減らす運動に挑戦しました。その結果、少し減少しました。今でもテレビのスイッチを元から切る癖がついているので、リモコンが使えない時があります(笑)
(勝山市 事務員 女性)
マイバッグやリサイクルのスーパー袋をだすと、喜んでくれるお店と嫌な顔をするお店があります。後者は「遅れているなあ」と思います。店頭で『地球の為に袋を持参いただけると助かります』のような、ステッカー等をした方がいいと思います。
(福井市 主婦 女性)
安全で安心して食べられる野菜づくりに取り組んでいるので葉一枚も捨てるという事もなく、果物等の皮などはコンポストを利用して肥料として再利用しています。特集を読んで、一人ひとりが出来る事をするように考え合う場を広げていきたいと思いました。
(福井市 主婦 女性)
少しでも地球にやさしいように、自分のできることは実践したいと日々追求しています。
(鯖江市 主婦 女性)
地域における環境保全活動などの中心となる人材を育成することを目的に「環境活動リーダー育成講座」を開催しました。
基礎講座延べ五八名、応用講座延べ六八名の方が参加され、各講座とも全日程受講された方には修了証が授与されました。
| 開催日・場所 | テーマ | 講師 | 内容 | 参加者からの感想・意見 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎講座 | ||||
| 第1回 10月2日(土) 県衛生環境研究センター |
和やかな雰囲気づくりを学ぶ(アイスブレイキング | GNOM自然環境教育事務所 代表 坂本均氏 |
・アイスブレイキングの実践 |
・アイスブレイキングを体験し、注意点や目的などがわかった ・プログラムの編成により、リーダーの指導性が表れる |
| 福井県の環境の概況を知る | 県衛生環境研究センター 坪内彰氏 |
・透視度測定 ・大気汚染監視テレメータシステムの見学 |
・環境測定データがリアルタイムに集中管理されている事に感心した ・環境とは、変化を感じる(調べる)ということ |
|
| 第2回 10月16日(土) 県生活学習館 |
水生生物による水質調査 | NPO法人 田んぼの学校越前大野 学校長 高津琴博氏 |
・水生生物の調べ方 ・水質を規定する環境要素について |
・水質のみにこだわらなくても、水生生物相からは水質以外の情報も知る事ができると分かった |
| NPOの組織づくり | NPO法人 赤目の里山を育てる会理事 伊井野雄二氏 |
・組織づくりってなに? ・組織として一番大事な事について |
・一人の活動が多くの人たちに影響を与え、信用信頼により組織としてステップアップしていくことが分かった ・お金がなくても実現できる事業はたくさんあるということ |
|
| 第3回 10月30日(土) 県生活学習館 |
実践!エコライフ | びわ湖会議事務局長 宮川琴枝氏 |
・水のパックテストの実践 ・ゴミ、温暖化などについて |
・買い物袋の事など一人ひとりが意識して訴えていく事が大切だと感じた |
| 環境教育プログラム体験 | 木曾三川公園 環境教育専門員 神谷佐緒理氏 |
・どんな時に水を使っているか考える ・水の旅(山から海まで)を体験 |
・汚れた水はどこへいくのか?蒸発したからといって川の水がきれいになるわけではないんですね… |
|
| 応用講座 | ||||
| 第1回 11月20日(土) 県文書館 |
環境教育プログラム の活用方法を学ぶ |
木曾三川公園 環境教育専門員 神谷佐緒理氏 |
・アイスブレ―キング ・環境教育プログラムの体験 「食べている水」 |
・身近なところで環境を考えるヒントがたくさんあり、足元から学ぶ事ができた ・興味を引き寄せながら説明していく事が大切なんですね |
| 第2回 11月27日(土) 県文書館 |
インタープリテーション (環境の大切さを伝えよう) |
自然教育研究センター 主任研究員 古瀬浩史氏 |
・インタープリテーション(体験を通して事象の背後にある意味を明らかにしていくこと、啓発に近い)について ・野外での葉っぱを使ったプログラム体験 |
・インタープリテーションの進め方は多様多種で「力量・人柄・知識」が加わる。まずは、自分磨きから始めないと… ・人に伝える事の難しさを知った ・大切なのは参加者に想像させ、体験させ、理解させること |
| 第3回 12月4日(土) 県文書館 |
思いをカタチに (グループ活動の企画と ワークショップ) |
GNOM自然環境教育事務所 代表 坂本均氏 |
・活動団体の事業案作成 ・企画立案の全体像について |
・事業計画の立て方について、マーケティングをおろそかにしている自分に気づいた 一人よがりになっていたのかも ・実施したい事を明確にしておくことが成功につながること |
●修了者名簿●
基礎講座(十名)
大河内 肇 海道 美紀雄 笠松 徳蔵 下元 重治 大門 健一 高橋 重彦 武澤 衛 中屋 弘 花木 鐵男 松山 幸広
応用講座(十九名)
井口 幸恵 大河内 肇 岡田 哲郎 海道 美紀雄 笠松 徳蔵 金倉 奈美 下元 重治 大門 健一 高橋 重彦 武澤 衛 竹元 隆夫 多田 喜代子 徳永 洋子 中島 早苗 中屋 弘 野村 昭一 花木 鐵男 増田 敬 村上 和子
(敬称略)
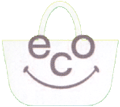 |
あたりまえを |
おかげさまで、
188,575枚※のレジ袋を
減らすことができました。
※37,715通×5枚
お買物の際、レジ袋をお断りになった方にスタンプを押すマイバッグスタンプラリーを実施したところ、多数のご参加をいただきました。本キャンペーンにご協力いただきました県民の皆様、事業者の方々および関係各位に厚くお礼申し上げます。
なお、このほど厳正な抽選会を行い賞品の当選者を決定しました。(お名前を県のホームページに掲載中。http://info.pref.fukui.jp/haitai/index.html)
応募状況について
キャンペーン実施期間:平成16年10月1日から10月31日まで
応募総数・・・37,715通(昨年の3.3倍)
使われなかったレジ袋の数・・・188,575枚(昨年の5.5倍)
■お問い合わせ/福井県廃棄物対策課リサイクル推進室
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 TEL.0776-20-0382(直通)
車の燃料となるガソリンや軽油の消費、石油・ガス・電気の使用などによって、二酸化炭素が大量に大気中に放出されています。その結果、私たちが気づかないうちに、地球温暖化が進行しているのです。
冬期の暖房需用が増える2月。省エネルギーの大切さを認識し、できることから実践してみませんか?
県では、環境に関する学習会等を、活動団体や公民館、地域のグループなどが開催する場合、講師として環境アドバイザーを派遣しています。 現在、環境汚染・自然環境・地域活動など7分野に環境アドバイザーが登録されています。派遣は年に20回程度を予定しており、予算の範囲内において、派遣に対する謝金および交通費を負担します。
派遣を希望される方や詳細を知りたい方は、県環境政策課までご連絡ください。
また、みどりネット http://www.erc.pref.fukui.jp/
でもアドバイザーの名簿など詳細を掲載していますので御覧ください。
問合せ先:福井県福祉環境部環境政策課 TEL 0776−20−0301
環境ふくい推進協議会では、随時会員を募集しています。
環境問題に関心のある方、本紙『みんなのかんきょう』を毎号読みたい方、当協議会主催行事等の情報を知りたい方は、ぜひご入会ください。お待ちしております!
《年会費》個人会員:500円
企業会員:10,000円(1口以上何口でも可)
団体会員:無料
《申込み・問合せ先》
環境ふくい推進協議会事務局(福井県環境政策課内)
TEL 0776−20−0301
2月に京都議定書が発効します。今後、ますます温暖化防止に向けた取組みが重要になってきます。現状は温室効果ガスの削減どころか、増加しているとのこと。原因は様々ですが、私たちの何気ない日常生活も原因のひとつ。省エネ月間にあわせて、アイドリングストップや暖房器具等の使い方など、"効率的なエネルギー使用"を考えてみましょう。
(ぬ)