娐嫬傆偔偄悇恑嫤媍夛偺忣曬巻
| 傒傫側偺偐傫偒傚偆 |
戞俁俇崋丂暯惉15擭9寧敪峴
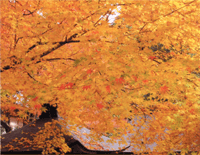 |
亂庡側撪梕亃 ///丂傆傞偝偲娐嫬帺枬丂/// 扥惗孲 挬擔挰丂乽墇抦嶳偲偦偺廃曈乿 ///丂摿丂廤丂/// 惗妶偺拞偺壔妛暔幙 ///丂巹払偺妶摦徯夘丂/// |
|
昞巻幨恀 | |
娐嫬傆偔偄悇恑嫤媍夛偺忣曬巻
| 傒傫側偺偐傫偒傚偆 |
戞俁俇崋丂暯惉15擭9寧敪峴
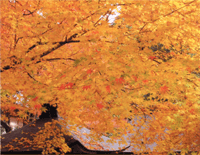 |
亂庡側撪梕亃 ///丂傆傞偝偲娐嫬帺枬丂/// 扥惗孲 挬擔挰丂乽墇抦嶳偲偦偺廃曈乿 ///丂摿丂廤丂/// 惗妶偺拞偺壔妛暔幙 ///丂巹払偺妶摦徯夘丂/// |
|
昞巻幨恀 | |
乽墇抦嶳偲偦偺廃曈乿丂丂扥惗孲 挬擔挰
墇抦嶳(偍偪偝傫)偼丄扥惗嶳抧偺傎傏拞墰晹偵埵抲偟丄怐揷挰偲暉堜巗乮揳壓(偱傫偑)抧嬫乯偵椬愙偡傞挬擔挰偺旘傃抧偱丄墇慜壛夑崙掕岞墍偵巜掕偝傟偰偄傑偡丅嶳捀偵棫偮偲丄擔杮奀偼傕偲傛傝丄擔杮嶰柤嶳偺堦偮偱偁傞敀嶳楢曯傗墇慜晉巑乮擔栰嶳乯丒庒嫹晉巑乮惵梩嶳乯傑偱尒搉偡偙偲偑偱偒丄傑偝偵帺慠偺揥朷戜偱偡丅
傑偨嶳捀偵偼丄撧椙帪戙偵懽悷戝巘(偨偄偪傚偆偨偄偟)偑奐偄偨偲揱偊傜傟偰偄傞墇抦恄幮偑偁傝丄偙傟傪拞怱偲偡傞暥壔偼丄姍憅帪戙弶婜偐傜幒挰帪戙偵偐偗偰斏塰傪嬌傔傑偟偨丅
懽悷戝巘偼丄暿柤乽墇(偙偟)偺戝摽(偩偄偲偙)乿偲傕屇偽傟傞揱愢偺崅憁偱偡丅懌愓偼丄導撪偼傕偲傛傝撧椙丒嫗搒側偳偺嬤導偐傜嶳宍導偵傑偱帄偭偰偄傑偡丅偦偺撪梕偼丄幮帥偺奐婎傗暓憸偺帺嶌埨抲丄堛椕娭學偺晛媦丒帯嶳帯悈帠嬈偺巜婗丒惔悈傗壏愹偺敪尒側偳懡婒偵搉傝丄慡崙偱栺嶰昐儢強偵偍偄偰妋擣偝傟偰偄傑偡丅
 |
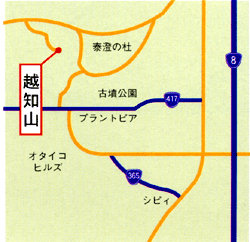 |
| 懽悷戝巘憸 | 抧恾 |
峏偵丄尦惓(偘傫偟傚偆)揤峜乮嵼埵幍廫屲擭乣幍擇巐擭乯偑昦杺偵庢傝晅偐傟偰庤偺巤偟傛偆偑側偔丄戝曄崲偭偰偄偨偲偙傠丄懽悷戝巘偺塡傪暦偄偨揤峜壠偱偼丄戝巘傪枍尦偵屇傃帯椕傪埶棅偟傑偟偨丅戝巘偑昦婥暯桙偺婩婅傪偟偨偲偙傠丄偨偪傑偪偺偆偪偵夞暅偟偨偲偄偆偙偲偱偡丅
偙傟傜偺壎徿偵傛傝丄乽懽悷(偨偄偪傚偆)乿偺彯崋偲挬掛偺偪傚偔偑傫偟傚捄婅強傪庴偗偨偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅
 |
 |
| 僀儚僇僈儈 | 儂僂僲栘偺壴 |
堦曽墇抦嶳偼丄昗崅乮613m乯偑崅偔偼偁傝傑偣傫偑丄懳攏抔棳偲搤偺婫愡晽偺塭嬁傪庴偗偰怉惗偑朙偐偱僽僫偺揤慠椦側偳偑曐懚偝傟偰偄傑偡丅懠偵丄栰捁傗崺拵椶偺惗懅偑懡偄偲尵傢傟偰偄傑偡丅
偁偝傂懽悷弇惗偺彫愳寷彶巵偵傛傞偲丄儂僂僲栘偺揤慠椦傗儐僉僶僞僣僶僉傗僀儚僇僈儈側偳憪壴椶傪崌傢偣傞偲悢昐庬椶偑帺惗偟丄摿偵栻梡怉暔椶偑懡偄偲偄偆偙偲偱偡丅
傑偨丄嶁揷庣惓巵乮暉堜巗嵼廧乯偼丄乽儂僞儖丒僩儞儃丒僋儚僈僞丒僶僢僞側偳丄埲慜擾懞抧堟偱擔忢偵栚偵偟偰偄偨崺拵椶偑傎偲傫偳惗懅偟偰偍傝丄戝棨偐傜搉偭偰偔傞捁椶傗僠儑僂僠儑偺旘傇摴偑巆偭偰偄傞乿偲岅傜傟偰偄傑偡丅 傑偨丄嶳偺尒偛傠偼怴夎偑慛傗偐偱丄摿偵楢媥偺崰偼庬乆偺庽栘偑奺乆堎側偭偨怓偺怴夎傪揥奐偡傞偺偱丄弔偵傕峠梩偑偁傞偺偐偲嬃偒傑偡丅
 |
| 悈堸傒応 |
壞偵偼丄僒儐儕側偳偺憪壴椶傗娏栘椶偑壴傪嶇偐偣偰啵枱(傜傫傑傫)傪嫞偄傑偡丅傑偨丄僽僫偺揤慠椦傪捠傝敳偗傞偲丄偙傕傟傃傪梺傃側偑傜怱抧傛偄晽偵弌夛偭偰壗偲傕尵偊偸偡偑偡偑偟偄枮懌姶傪枴傢偆偙偲偑偱偒傑偡丅搊嶳摴桞堦偺悈堸傒応偼丄僽僫偺戝栘偺娫偺娾寠偐傜桸悈偟偰偄傑偡丅揱愢偵傛傞偲丄懽悷戝巘偑撈屫媙(偲偭偙偆偒偹)乮暓嬶乯傪巊偭偰戝娾偵偆偐偑偭偰媮傔偨楈愹偩偲偄傢傟偰偍傝丄擭拞愨偊傞偙偲側偔丄朘傟傞恖乆偺岮傪弫偟偰偔傟傑偡丅
廐偼丄揤慠椦堦懷傗庬乆偺棊梩庽偑墿怓傗峠怓偵怓偯偒丄戝曄尒帠偱偡丅
搤偼丄僣僶僉側偳偺奐壴傗愥壔徬偑尒傜傟傑偡偑丄愊愥偑傗傗懡偄偺偱丄孭楙偝傟偨曽乆偵偺傒偍姪傔偟傑偡丅
偲偵偐偔丄堦搙偍弌偐偗偔偩偝偄丅
乮揤墹愳旤壔悇恑嫤媍夛戙昞 偁偝傂懽悷弇惗丂屼浽 媊帇乯
仠傆傞偝偲偺娐嫬帺枬曞廤拞両両
奆偝傫偺屘嫿帺枬偱堦儁乕僕傪忺傝傑偣傫偐丅愮帤掱搙偺尨峞偵抧恾丒幨恀傪揧晅偟偰墳曞偟偰偔偩偝偄丅応強偺徯夘偩偗偱傕寢峔偱偡丅
嵦梡偝傟偨曽偵偼婰擮昳傪偍憲傝偟傑偡丅
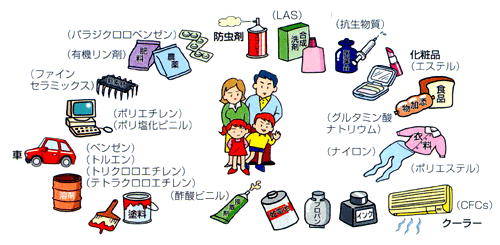 |
巹偨偪偺恎偺夞傝偵偼壔妛暔幙偑偁傆傟偰偄偰丄偦傟傜偼巹偨偪偺惗妶傪朙偐偵曋棙偵偟偰偔傟傑偡丅
悽奅拞偱奐敪偝傟偨壔妛暔幙偺忣曬傪廂廤偟偰偄傞暷崙偺婡娭偵偼丄侾俉侽侽枩庬埲忋偺壔妛暔幙偑搊榐偝傟丄偦偺拞偺偍傛偦侾侽枩庬偺壔妛暔幙偑幚嵺偵巊傢傟偰偄傞偲偄傢傟偰偄傑偡丅
偦偆偟偨懡悢偺壔妛暔幙偦偺傕偺丄偁傞偄偼偦傟傜傪娷傓惢昳傗娐嫬墭愼暔幙偼丄惗懺宯傗恖偺寬峃偵塭嬁傪媦傏偟丄娐嫬墭愼傪堷偒婲偙偡傕偺傕偁傝傑偡丅
偦偙偱崱夞偼惗妶偺側偐偺壔妛暔幙丄摿偵幒撪嬻婥拞偺壔妛暔幙偺塭嬁偵傛傞乽僔僢僋僴僂僗徢岓孮乿偵偮偄偰峫偊偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅
仧僔僢僋僴僂僗徢岓孮偲偼丠
嬤擭丄怴抸傗夵抸屻偺廧戭側偳偱丄廧戭偺崅婥枾壔傗壔妛暔幙傪敪嶶偡傞寶嵽傗撪憰摍偵傛傞幒撪偺嬻婥墭愼偵傛偭偰丄擖嫃偟偨恖偵栚偑僠僇僠僇偡傞丄岮偑捝偄丄傔傑偄傗揻偒婥丄摢捝偑偡傞側偳偺偝傑偞傑側懱挷晄椙偑惗偠偰偄傞偲偄偭偨慽偊偑曬崘偝傟偰偄傑偡丅
徢忬偑懡條偱丄徢忬傪敪惗偝偣傞巇慻傒側偳枹夝柧側晹暘偑懡偔丄寶嵽摍偐傜偺壔妛暔幙偺敪嶶検丄寶抸暔偺愝寁丒巤岺曽朄丄姺婥側偳偺廧傑偄曽丄壠嬶傗擔梡昳側偳偺塭嬁丄抔朳摍偺擱從僈僗丄僇價丒僟僯摍偺傾儗儖僎儞丄壔妛暔幙摍偵懳偡傞姶庴惈偺屄恖嵎側偳丄偝傑偞傑側暋崌梫場偑峫偊傜傟傞偙偲偐傜丄偙傟傜傪憤徧偟偰乽僔僢僋僴僂僗徢岓孮乿偲屇傫偱偄傑偡偑丄堛妛揑偵掕媊偝傟偨昦柤偱偼偁傝傑偣傫丅
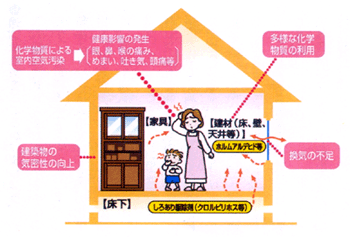 |
仧僔僢僋僴僂僗徢岓孮偼偳傫側徢忬偑尰傟傞偺偱偡偐
壆奜偵偄傞偲偒偼徢忬偑側偄偺偵丄廧戭傗價儖偺拞偵擖偭偨帪偵師偺傛偆側徢忬傪慽偊傞応崌偵偼丄幒撪娐嫬偵尨場偑偁傞偐傕偟傟傑偣傫丅堛椕婡娭傗曐寬強側偳偵憡択偟丄揔愗側懳墳傪偲傝傑偟傚偆丅
丒栚偵巋寖姶偑偁傝丄僠僇僠僇偡傞丅
丒摢捝傗傔傑偄丄揻偒婥偑偡傞丅
丒旲悈傗椳丄偣偒偑弌傞丅
丒旲傗偺偳偑姡憞偟偨傝丄巋寖姶傗彎傒偑偁傞丅
丒壗偲側偔旀傟傪姶偠偨傝丄柊婥偑偡傞丅
丒旂晢偑姡憞偟偨傝愒偔側偭偨傝偐備偔側傞丅
仧僔僢僋僴僂僗徢岓孮偼側偤偍偒傞偺偱偡偐
師偺俁偮偺偙偲偑峫偊傜傟傑偡丅
丒廧戭偵巊梡偝傟偰偄傞寶嵽丄壠嬶丄擔梡昳側偳偐傜條乆側壔妛暔幙偑敪嶶偡傞丅
丒廧戭偺婥枾惈偑崅偔側偭偨偙偲丅
丒儔僀僼僗僞僀儖偑曄壔偟姺婥偑晄懌偟偑偪側偙偲丅
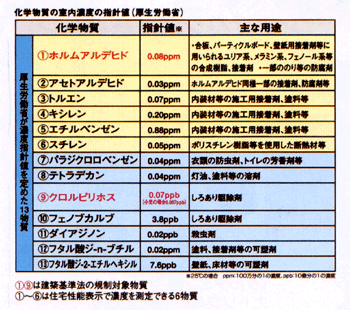 |
仧僔僢僋僴僂僗徢岓孮偵懳偡傞奺徣挕偺庢慻傒偼丠
崙偱偼丄暯惉侾俀擭係寧偵乽僔僢僋僴僂僗懳嶔娭學徣挕楢棈夛媍乿傪愝抲偟岤惗楯摥徣丄娐嫬徣丄暥晹壢妛徣摍俇徣挕偑楢実偟偰僔僢僋僴僂僗憤崌懳嶔傪悇恑偟偰偄傑偡丅
岤惗楯摥徣偱偼幒撪嬻婥拞壔妛暔幙偺巜恓抣傪弴師愝掕偟丄尰嵼傑偱偵儂儖儉傾儖僨僸僪丄僩儖僄儞側偳侾俁暔幙偵偮偄偰巜恓抣傪愝掕偟偰偄傑偡丅
暥晹壢妛徣偱偼暯惉侾係擭係寧傛傝嫵幒摍偺嬻婥偺専嵏崁栚偵儂儖儉傾儖僨僸僪摍係暔幙傪捛壛偟掕婜専嵏傪媊柋晅偗傑偟偨丅傑偨丄僐儞僺儏乕僞摍怴偨側旛昳偺斃擖摍偵傛傝敪惗偺嫲傟偑偁傞偲偒傗丄怴抸丒夵抸摍偑峴傢傟偨応崌偵偼椪帪偺専嵏傪峴偄丄婎弨傪壓夞偭偰偄傞偙偲傪妋擣偟側偗傟偽側傜側偄偲偝傟傑偟偨丅
崙搚岎捠徣偱偼暯惉侾俁擭俉寧傛傝廧戭惈擻昞帵偵怴偨側昞帵崁栚偲偟偰儂儖儉傾儖僨僸僪側偳偺擹搙昞帵崁栚傪捛壛偟傑偟偨偑丄崱擭俈寧偵偼偝傜偵僔僢僋僴僂僗徢岓孮偵懳偡傞婯惂傪嫮傔傞偨傔丄朄棩偺夵惓傪峴偄傑偟偨丅
仧侾俆擭俈寧侾擔偐傜巤峴偝傟偨寶抸婎弨朄夵惓偺撪梕偼丠
僔僢僋僴僂僗偺尨場偲側傞壔妛暔幙偺幒撪擹搙傪壓偘傞偨傔丄廧戭丄妛峑丄僆僼傿僗丄昦堾摍慡偰偺寶抸暔偺嫃幒傪懳徾偵丄寶抸暔偵巊梡偡傞寶嵽傗姺婥愝旛傪婯惂偡傞偨傔偺朄棩夵惓偱丄撪梕偼師偺偲偍傝偱偡丅
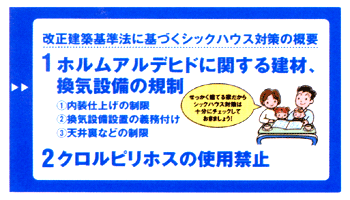 |
侾 儂儖儉傾儖僨僸僪偵娭偡傞寶嵽丄姺婥愝旛偺婯惂
儂儖儉傾儖僨僸僪偼巋寖惈偺偁傞婥懱偱栘幙寶嵽側偳偵巊傢傟偰偄傑偡偑丄師偺俁偮偺慡偰偺懳嶔偑昁梫偲側傝傑偡丅
嘆撪憰巇忋偘偵巊梡偡傞儂儖儉傾儖僨僸僪傪敪嶶偡傞寶嵽偺柺愊惂尷傪偟傑偡丅
嘇儂儖儉傾儖僨僸僪傪敪嶶偡傞寶嵽傪巊梡偟側偄応崌偱傕丄壠嬶偐傜偺敪嶶偑偁傞偨傔丄尨懃偲偟偰嫃幒傪桳偡傞慡偰偺寶抸暔偵婡夿姺婥愝旛偺愝抲傪媊柋晅傜傟傑偟偨丅
嘊揤堜棤丄彴壓丄暻撪丄廂擺僗儁乕僗側偳偐傜嫃幒傊偺儂儖儉傾儖僨僸僪偺棳擖傪杊偖偨傔丒寶嵽偵傛傞慬抲丒婥枾憌丄捠婥巭傔偵傛傞慬抲丒姺婥愝旛偵傛傞慬抲偺偄偢傟偐偺慬抲偑昁梫偱偡丅
俀 僋儘儖僺儕儂僗偺巊梡嬛巭
嫃幒傪桳偡傞寶抸暔偵偼丄桳婡儕儞宯偟傠偁傝嬱彍嵻偺僋儘儖僺儕儂僗偺巊梡偑嬛巭偝傟傑偟偨丅
仧僔僢僋僴僂僗懳嶔偼偙傫側偲偙傠偵婥傪偮偗傑偟傚偆丅
寶抸婎弨朄偝偊庣傟偽僔僢僋僴僂僗懳嶔偼廫暘丄偲偄偆傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅廧戭慖傃偵摉偨偭偰偼丄僩儖僄儞丄僉僔儗儞側偳懠偺壔妛暔帒懳嶔傕偟偭偐傝僠僃僢僋偟傑偟傚偆丅傑偨丄壠嬶傗杊拵嵻丄壔徬昳丄僞僶僐丄僗僩乕僽側偳傕壔妛暔幙偺敪惗尮偲側傝傑偡丅恎偺夞傝偺擔梡昳傗姺婥側偳丄廧傑偄曽偵傕廩暘婥傪偮偗傑偟傚偆丅
仠揔愗側姺婥傪偙偙傠偑偗傑偟傚偆丅
丒俀係帪娫姺婥僔僗僥儉偺僗僀僢僠偼愗傜偢偵丄忢偵塣揮偡傞傛偆偵偟傑偡丅
丒怴抸傗儕僼僅乕儉摉弶偼丄幒撪偺壔妛暔幙偺敪嶶偑懡偄偺偱丄偟偽傜偔偺娫偼丄姺婥傗捠晽傪廫暘峴偆傛偆怱偑偗傑偡丅
丒摿偵壞偼壔妛暔幙偺敪嶶偑憹偊傞偺偱幒撪偑挊偟偔崅壏崅幖偲側傞応崌偵偼憢傪暵傔愗傜側偄傛偆偵偟傑偡丅
丒憢傪奐偗偰姺婥偡傞応崌偵偼丄暋悢偺憢傪奐偗偰丄墭愼嬻婥傪攔弌偡傞偲偲傕偵怴慛側嬻婥傪摫擖偡傞傛偆偵偟傑偡丅
丒姺婥愝旛偼僼傿儖僞乕偺惔憒側偳掕婜揑偵堐帩娗棟偟傑偡丅
仠壔妛暔幙偺敪惗尮偲側傞傕偺傪側傞傋偔尭傜偟傑偟傚偆丅
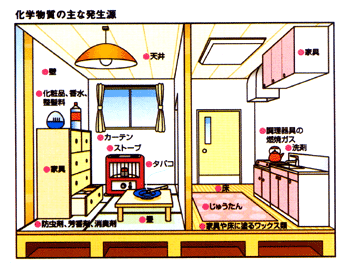 |
丒怴偟偄壠嬶傗僇乕僥儞丄偠傘偆偨傫偵傕壔妛暔幙傪敪嶶偡傞傕偺偑偁傞偺偱拲堄偑昁梫偱偡丅
丒壠嬶傗彴偵揾傞儚僢僋僗椶偵偼丄壔妛暔幙傪敪嶶偡傞傕偺偑偁傞偺偱拲堄偑昁梫偱偡丅
丒杊拵嵻丄朏崄嵻丄徚廘嵻丄愻嵻側偳傕敪惗尮偲側傞偙偲偑偁傝傑偡丅
丒壔徬昳丄崄悈丄惍敮椏側偳傕塭嬁偡傞偙偲偑偁傝傑偡丅
丒幒撪偱僞僶僐傪媧偆偙偲偼旔偗傑偟傚偆丅
丒奐曻宆僗僩乕僽傗僼傽儞僸乕僞乕摍攔婥傪幒撪偵弌偡抔朳婍嬶偺巊梡偼旔偗丄俥俥幃僗僩乕僽摍攔婥傪奜晹偵弌偡幒撪嬻婥偺墭愼偑彮側偄抔朳婍嬶傪巊梡偡傞傛偆偵偟傑偟傚偆丅
仧壔妛暔幙夁晀徢偲偼偳偆偄偆傕偺偱偡偐丠
壔妛暔幙夁晀徢傕幒撪嬻婥拞偺壔妛暔幙偵傛偭偰堷偒婲偙偝傟傞徢忬偱偡丅
堦搙偵戝検偺壔妛暔幙偵愙偟偨傝丄彮偟偢偮挿婜偵摿掕偺壔妛暔幙偵偝傜偝傟傞偲丄偁傞偲偒偐傜恎懱偑壔妛暔幙偵夁忚偵斀墳偡傞傛偆偵側偭偰偟傑偄傑偡丅
恖懱偑壔妛暔幙傪庴偗擖傟傞偙偲偺偱偒傞乽僐僢僾乿傪帩偭偰偄傞偲壖掕偟傑偡丅偦偺乽僐僢僾乿偑偄偭傁偄偵側傝丄堨傟弌偟偰偟傑偆偲嬌旝検偺壔妛暔幙偵懳偟偰斀墳偟偰偟傑偄傑偡丅偙偺傛偆偵壔妛暔幙偵夁晀偵斀墳偡傞恖傪丄壔妛暔幙夁晀徢偲尵偄傑偡偑丄惓幃側昦柤偱偼偁傝傑偣傫丅
恖偵傛偭偰僐僢僾偺戝偒偝偑堘偆偺偱丄壠懓偺拞偱傕夁晀偵斀墳偡傞恖偲丄斀墳偟側偄恖偑偱偰偒偰丄偦偺偨傔丄壠掚撪偺壔妛暔幙偑尨場偩偲擣幆偡傞偙偲偑側偐側偐擄偟偄偙偲偲側偭偰偄傑偡丅
敪徢偺尨場偲峫偊傜傟傞壔妛暔幙偼侾庬椶偱傕丄堦扷敪徢偟偰偟傑偆偲懡庬椶偺壔妛暔幙偵懳偟偰丄嬌抂偵旝検偱傕夁晀偵斀墳偟偰偟傑偆偺偱惗妶寳偑嫹傑傝丄廳徢偵側傞偲巇帠傗擔忢惗妶傪塩傔側偄忬懺偵側偭偰偟傑偄傑偡丅
尨場晄柧偺懱挷晄椙偼丄壔妛暔幙偵傛傞夁晀徢傪媈偭偰傒傞偙偲偑昁梫偱偡丅
僔僢僋僴僂僗徢岓孮傕壔妛暔幙夁晀徢偺堦庬偲峫偊傜傟傑偡丅
壔妛暔幙夁晀徢偺尨場偲側傞壔妛暔幙偼丄戙昞揑側暔幙偼傎傏僔僢僋僴僂僗徢岓孮偲摨偠偱偡偑丄偦偺懠偺椺偲偟偰偼怘昳揧壛暔側偳偑偁傝傑偡丅
愄偵斾傋丄僔僢僋僴僂僗徢岓孮傗壔妛暔幙夁晀徢偺恖偑憹偊偰偒偨攚宨偵偼丄恎偺夞傝偺壔妛暔幙偑憹偊偰丄忢偵偄傠偄傠側壔妛暔幙偵怗傟偰偄傞偙偲丄偦偟偰摥偔娐嫬傗曌嫮傪偡傞娐嫬偑曄壔偟丄惛恄揑丄擏懱揑偵傕僗僩儗僗偑懡偔側偭偰偄傞偙偲偑偁偘傜傟傑偡丅
壴暡徢傗傾僩僺乕傕愄偼偁傑傝暦偐側偐偭偨昦婥偱丄尰戙偺恖偺恎懱傪庣傞僔僗僥儉偑庛偔側偭偰偒偨偺偱偼側偄偐偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅
偦偙偱丄恖偑杮棃帩偭偰偄傞乽恎懱傪庣傞杊屼斀墳乿傪嫮偔偡傞偙偲偑廳梫偱偁傝丄偦偺偨傔偵偼師偺偙偲偵怱偑偗傑偟傚偆丅
丒婯懃揑側惗妶偲悋柊帪娫傪廫暘偵偲傞丅
丒揔搙偺塣摦傪偡傞丅
丒怘帠偺帪娫傪傑傕傝丄僶儔儞僗偺傛偄怘帠傪偲傞丅
丒僗僩儗僗傪旔偗傞丅
仧傾儗儖僊乕偲壔妛暔幙夁晀徢偼偳偆堘偆偺偱偡偐丠
傾儗儖僊乕偼丄懱偑杮棃帩偭偰偄傞柶塽斀墳偑夁忚偵婲偒偰偟傑偆偙偲偐傜尰傟傞偄傠偄傠側徢忬偺偙偲偱偡丅
恖娫偵偼丄懱偺拞偵桳奞側嵶嬠傗壔妛暔幙偑擖偭偰偒偨偲偒丄偦傟傪嵶朎偺拞偵庢傝崬傫偱嶦偡偐丄撆惈傪庛偔偟偰懱偺奜偵攔弌偟傚偆偲偡傞峈懱偺摥偒偑旛傢偭偰偄偰丄偙傟傪柶塽斀墳偲偄偄傑偡丅
懱偵擖偭偨嵶嬠傗壔妛暔幙偲愴偆柶塽斀墳偼丄傢傟傢傟偑惗懚偟偰偄偔偨傔偵昁恵偺傕偺偱偡偑丄傾儗儖僊乕偺恖偼偙偺斀墳偑夁忚偵婲偙偭偰偟傑偄傑偡丅奜晹偐傜擖偭偰偒偨傾儗儖僎儞乮峈尨乯偵丄懱偺拞偵偁傞峈懱偑寖偟偔斀墳偟偰婲偙傞徢忬偑傾儗儖僊乕偱偡丅偙傟偵懳偟丄壔妛暔幙夁晀徢偼恄宱宯偺夁晀斀墳偱偁傞揰偵堘偄偑偁傝傑偡丅
夁晀徢偵偐偐傝傗偡偄偲偄傢傟偰偄傞彫帣傗柶塽椡偺掅壓偟偨榁恖丄峏擭婜偺彈惈偺偄傞壠掚偱偼丄摿偵壔妛暔幙傪敪嶶偡傞廧戭帒嵽傗壠嬶偺巊梡傪旔偗偨傝丄偙傑傔側姺婥偵怱偑偗丄夣揔偱寬峃側惗妶傪憲傟傞傛偆偵偟傑偟傚偆丅
亂弌揟亃
侾乯(幮)娐嫬忣曬壢妛僙儞僞乕丂曇廤乛俹俼俿俼僨乕僞傪撉傒夝偔偨傔偺巗柉僈僀僪僽僢僋 壔妛暔幙偵傛傞娐嫬墭愼傪尭傜偡偨傔偵丂乮2003.3乯
俀乯崙搚岎捠徣丂敪峴乛僔僢僋僴僂僗僷儞僼儗僢僩
杒棨揹椡姅幃夛幮
乣 杒棨揹椡偺娐嫬曐慡妶摦 乣
摉幮偼丄乽杒棨揹椡21悽婭娐嫬寷復乿傪婎杮偲偟丄抧媴壏抔壔杊巭偵岦偗偨尨巕椡丄徣僄僱儖僊乕丄怴僄僱儖僊乕偺堦憌偺悇恑傗丄愇扽奃偺桳岠妶梡傗僾儔僗僠僢僋儕僒僀僋儖帠嬈側偳偺揥奐偵傛傞弞娐宆幮夛宍惉偺偨傔偺俁俼偺悇恑側偳丄娐嫬晧壸掅尭偵帒偡傞偝傑偞傑側庢傝慻傒傪悇恑偟偰偄傑偡丅
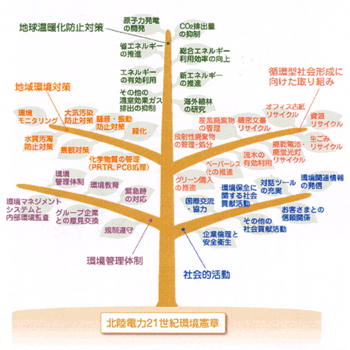 |
[杒棨揹椡21悽婭娐嫬寷復]
仠婎杮棟擮
憤崌僄僱儖僊乕抦幆嶻嬈偲偟偰丄娐嫬傊偺偄偨傢傝傪戝愗偵丄抧媴娐嫬曐慡偵搘傔傞偲偲傕偵丄弞娐宆幮夛偺宍惉傪傔偞偟傑偡丅
仠峴摦愰尵
僄僱儖僊乕偺埨掕嫙媼偲宱塩岠棪壔偲偺椉棫傪偼偐傞偲偲傕偵丄廧傒椙偄幮夛偺幚尰偵岦偗偰丄廬嬈堳堦恖傂偲傝偑堄幆傪怴偨偵偟偰丄娐嫬偺俀侾悽婭偵傆偝傢偟偄帠嬈妶摦傪悇恑偟傑偡丅
1. 抧媴壏抔壔杊巭懳嶔偺悇恑
2. 娐嫬曐慡懳嶔偺悇恑
3. 弞娐宆幮夛宍惉偵岦偗偨帠嬈妶摦偺悇恑
4. 偍媞偝傑偲堦懱偲側偭偨娐嫬曐慡妶摦偺揥奐
5. 娐嫬娗棟偺揙掙
(杒棨揹椡噴暉堜巟揦憤柋晹丂抧堟峀曬僠乕儉丂愇嶳丂桬晇乯
暉堜傪旤偟偔偡傞夛楢棈嫤媍夛
乣 夛偺桼棃 乣
徍榓係俁擭偵奐嵜偝傟偨丄暉堜崙懱帪偺乽壴偄偭傁偄塣摦乿偵偁偨傝丄摉帪巗撪奺抧偵偙偺庯巪偵巀摨偡傞儃儔儞僥傿傾抍懱丄摨岲抍懱摍偑惗傑傟傑偟偨丅偦偆偟偨抍懱傪曣懱偲偟偰丄徍榓係俈擭係寧偵乽抍懱憡屳偺楢棈丒楢実傪恾傝丄巗柉偺岞摽怱偺崅梘偵帒偡傞偲嫟偵丄旤壔偺懀恑偵婑梌偡傞乿偲偄偆栚揑偺傕偲偵丄侾俀偺扨埵抍懱偱夛傪寢惉偟丄崱擭俁俀擭栚偵側傝傑偡丅尰嵼侾係抍懱偑摑堦帠嬈偲偟偰乮巗柉寷復悇恑嫤媍夛偲偺嫟嵜偱乯師偺妶摦傪揥奐偟偰偄傑偡丅
 |
 |
| 憪壴昪懄攧夛偺條巕 | |
侾丏丂係寧忋弡偺俀擔娫丄弔偺憪壴昪懄攧夛傪奐嵜丅
俀丏丂俇寧侾擔偺僋儕乕儞傾僢僾傆偔偄戝嶌愴摍偺暉堜傪旤偟偔偡傞塣摦偵嶲壛丅
俁丏丂俇寧俀俉擔偺暉堜恔嵭婰擮擔偵摉帪傪幟傃丄憪壴昪偺懄攧夛傪奐嵜丅
係丏丂崱擭偼暉堜儅儔僜儞偺慜擔偵乽墂慜丒杮挰丒僼僃僯僢僋僗捠傝曕摴摍乿傪拞怱偵僋儕乕儞嶌愴傪幚巤丅
巹払偼丄娐嫬曐慡偲旤壔塣摦傪廳揰偵妶摦傪揥奐偟偰偍傝丄偙偆偟偨妶摦偼丄傂偲傝偱傕懡偔偺巗柉偺嶲壛偲幚慔偑戝愗偩偲巚偄傑偡丅
俀侾悽婭偼娐嫬偺悽婭偲偄傢傟偰偄傑偡丅夛堳堦摨婥帩偪怴偨偵丄栚揑払惉偵岦偗丄崱屻偲傕妶摦傪懕偗偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮暉堜傪旤偟偔偡傞夛楢棈嫤媍夛丂夛挿丂栰懞 徍堦乯
| 撉幰偺憢 |
(嶁堜孲丂戝妛惗丂抝惈)
(暉堜巗丂揾憰嬈丂抝惈)
(旤昹挰丂帺塩嬈丂抝惈)
(暉堜巗丂庡晈丂彈惈)
(彑嶳巗丂彫妛惗丂抝巕)
(暉堜巗丂岞柋堳丂彈惈)
(嶪峕巗丂抝惈)
儁僢僩儃僩儖偐傜儅僗僐僢僩傪嶌偭偨傛!!
乣恊巕娐嫬嫵幒傪奐嵜偟傑偟偨乣
|
壞媥傒拞偺峆椺峴帠偲側偭偨恊巕娐嫬嫵幒傪丄俉寧俀俁擔乮搚乯丄俀係擔乮擔乯偵弔峕挰偺暉堜導帣摱壢妛娰乮僄儞僛儖儔儞僪乯偱奐嵜偟傑偟偨丅椉擔偁傢偣偰彫妛惗偲偦偺曐岇幰傜憤惃俇係柤偑丄儕僒僀僋儖偵娭偡傞妛廗夛偲丄儁僢僩儃僩儖偐傜偱偒傞嵞惗柸偱僆儕僕僫儖偺儅僗僐僢僩傪偮偔傞岺嶌偵嶲壛偟傑偟偨丅
妛廗夛偱偼丄帒尮偺戝愗偝傗僾儔僗僠僢僋偺暘椶偺巇曽丄帺暘偨偪偵偱偒傞儕僒僀僋儖偵偮偄偰乽僾儔僗僠僢僋儕僒僀僋儖幚尡僲乕僩乿傪拞怱偵妛廗偟丄僾儔僗僠僢僋偐傜惗傑傟曄傢偭偨儃乕儖儁儞傗僕儍儞僷乕側偳偺彜昳傕徯夘偟傑偟偨丅 岺嶌乽僾儔僗僠僢僋偐傜嵞惗柸傪嶌傠偆両乿偱偼丄僗僞僢僼偺巜摫偺傕偲丄恊巕偱儅僗僐僢僩偯偔傝偵挧愴偟傑偟偨丅 5儈儕巐曽偵嵶偐偔愗偭偨僾儔僗僠僢僋偺僠僢僾傪嶌傝丄愱梡偺惢憿婡偵庢傝晅偗偨嬻偒娛偺拞偵擖傟丄僈僗僶乕僫乕偱偟偽傜偔抔傔傞偲丄僠僢僾偑梟偗偰嵶偐偔偁偗偨寠偐傜嵞惗柸偑傆傢傆傢偲柸壻巕偺傛偆偵偱偰偒傑偟偨丅 偙偺傛偆偵偟偰偱偒偨柸傪朹偵棈傔偲偭偰娵傔丄栚嬍傗栄巺丄僗僷儞僐乕儖側偳傪偮偗偰巚偄巚偄偺宍偵儅僗僐僢僩傪巇忋偘偰偄偒傑偟偨丅 偼偝傒傗壩傪巊偆嶌嬈偵傕丄恊巕偑嫤椡偟偰庢傝慻傒丄僆儕僕僫儖偺儅僗僐僢僩傪姰惉偝偣傑偟偨丅
巕偳傕偨偪偼丄儁僢僩儃僩儖偐傜柸偑偱偒偨偙偲偵偲偰傕嬃偄偨條巕偱偟偨丅曐岇幰偺曽偐傜偼丄乽恎嬤側帠偱娐嫬偺偨傔偵側傞偙偲偑偁傞偲暘偐偭偰婐偟偄丅岥偱巕偳傕偵愢柧偟偰傕揱偊傜傟側偄偙偲傪丄娙扨偵丄梀傃姶妎偱揱偊偰偄偨偩偄偰妝偟偐偭偨乿偲偄偭偨婐偟偄姶憐傕偄偨偩偒傑偟偨丅 |
仚傆偔偄儅僀僶僢僋僉儍儞儁乕儞俀侽侽俁仚
儅僀僶僢僌僗僞儞僾儔儕乕幚巤
侾侽寧侾擔乣侾侽寧俁侾擔
|
偍攦偄暔偺嵺丄攦偭偨傕偺傪儗僕戃偵擖傟偰傕傜偆偙偲傪摉偨傝慜偺偙偲偲偟偰偄傑偣傫偐丠 婜娫拞丄導撪偺僗乕僷乕側偳栺130偺嫤椡揦偵偰}僀僶僢僋僗僞儞僾儔儕乕饚缼{偟傑偡!! 嘆 偍攦偄暔偵嵺偟丄儅僀僶僢僋傪帩嶲偡傞丅 嘇 儗僕戃偺棙梡傪抐傝丄乽儅僀僶僢僋僗僞儞僾儔儕乕僇乕僪乿偵僗僞儞僾傪墴報偟偰傕傜偆丅 嘊 億僀儞僩傪俁屄廤傔偰丄暉堜導偵梄憲偱墳曞偡傞丅(嫤椡揦揦摢偱墳曞偼偑偒偺偍梐偐傝偼偄偨偟傑偣傫偺偱偛椆彸偔偩偝偄丅) 嘋 墳曞偟偰偄偨偩偄偨曽偺拞偐傜愭拝2,500恖偵儁僢僩儃僩儖嵞惗偺儅僀僶僢僌偐戜強梡悈愗傝僱僢僩傪丄拪慖偱500恖偵500墌暘偺彜昳寯傪嵎偟忋偘傑偡丅 嘍 墳曞掲愗丂暯惉侾俆擭侾侾寧侾擔乮搚乯丂摉擔徚報桳岠 仧偛傒傪尭傜偡偨傔丄帒尮偺傓偩巊偄傪杊偖偨傔偵丄偍攦偄暔偵偼儅僀僶僢僌傪帩偭偰弌偐偗傑偟傚偆丅 亂栤崌偣愭亃 暉堜導攑婞暔懳嶔壽丂儕僒僀僋儖悇恑幒 910-0580丂暉堜巗戝庤俁挌栚侾俈亅侾 Tel 0776-20-0382乮捈捠乯 E-mail haitai@ain.pref.fukui.jp |
娐嫬傆偔偄悇恑嫤媍夛偱偼丄奆條偐傜偺偍曋傝傪曞廤偟偰偄傑偡丅
仚 傆傞偝偲偺娐嫬帺枬仚
摉忣曬巻偺侾儁乕僕傪忺傞乽傆傞偝偲偺娐嫬帺枬乿傪曞廤偟傑偡丅偁傑傝抦傜傟偰偄側偄偲偭偰偍偒偺応強丄抧堟偱偺娐嫬傊偺庢傝慻傒摍傪楌巎揑側榖傗屄恖揑側僄僺僜乕僪傪偮偗偰徯夘偟偰傒傑偣傫偐丠
乮1000帤掱搙丂抧恾蕫^傕揧晅偟偰偔偩偝偄乯
仚 巹偨偪偺妶摦徯夘仚
娐嫬偵娭偡傞偙偲偱擔忢偱姶偠偰偄傞偙偲丄偪傚偭偲偟偨岺晇偱扤偵偱傕弌棃傞娐嫬曐慡妶摦丄僌儖乕僾妶摦偺徯夘側偳傪曞廤偟傑偡丅
乮500帤掱搙丂幨恀偑偁傟偽揧晅偟偰偔偩偝偄乯
仸嵦梡偝傟偨曽偵偼婰擮昳傪憲傜偣偰偄偨偩偒傑偡丅
娐嫬傆偔偄悇恑嫤媍夛偱偼丄悘帪夛堳傪曞廤偟偰偄傑偡丅
娐嫬栤戣偵娭怱偺偁傞曽丄杮巻亀傒傫側偺偐傫偒傚偆亁傪枅崋撉傒偨偄曽丄摉嫤媍夛庡嵜偺島墘摍偺忣曬傪抦傝偨偄曽偼丄偤傂屼擖夛偔偩偝偄丅偍懸偪偟偰偍傝傑偡丅
乻擭夛旓乼
屄恖夛堳丗俆侽侽墌
婇嬈夛堳丗侾岥 侾侽,侽侽侽墌
乮侾岥埲忋壗岥偱傕壜乯
抍懱夛堳丗柍椏
乻怽崬傒丒栤崌偣愭乼
娐嫬傆偔偄悇恑嫤媍夛帠柋嬊乮暉堜導娐嫬惌嶔壽撪乯
俿俤俴侽俈俈俇亅俀侽亅侽俁侽侾丂乮捈捠乯
曇仩廤仩屻仩婰
偛傒暘暿傪偟偰偄傞偲僾儔僗僠僢僋偺検偺懡偝偵嬃偒傑偡丅偟偐傕丄儕僒僀僋儖偱偒傞偺偼墭傟偰偄側偄鉟楉側傕偺傗愻偭偰墭傟偺棊偪傞傕偺偩偗乧儕僒僀僋儖傪偟傛偆偲偣偭偣偲愻偭偰傕丄崱搙偼悈偺巊梡検傗墭愼偑婥偵側傝傑偡丅揤傉傜桘傪僗僾乕儞1攖暘棳偡偲丄惗偒暔偑廧傔傞悈偵栠偡偵偼丄僪儔儉娛4攖暘乮栺俉侽侽儕僢僩儖乯偺悈偑昁梫偲尵傢傟偰偄傑偡丅娐嫬偺偙偲傪傕偭偲傕偭偲偄傠偄傠側曽岦偐傜峫偊側偄偲偄偗側偄側両偲夵傔偰姶偠傑偡丅丂丂乮俽乯