みんなのかんきょう |
第34号 平成15年4月発行
 |
|
(福井市足羽神社)
撮影/青木 誠
みんなのかんきょう |
 |
|
「立待小学校ビオトープ」 鯖江市
○学校ビオトープとは
「ビオトープ」とは直訳で「野生の生き物がくらせる場所」、さらに「本来その地域にすむ様々な野生の生き物が自立して生息することのできる、比較的均質な空間」とも定義されています。したがって「学校ビオトープ」とは、環境教育のための「地域のビオトープの見本」とか「地域のビオトープのミニチュアモデル」であるといえます。
鯖江市は、平成十一年度に制定された鯖江市環境基本計画に基づき、平成一二年度、鯖江市立待小学校に学校ビオトープ第一号を創設しました。
 |
 |
| 立待小学校ビオトープ | 立待小学校位置図 |
○全国優秀賞受賞
 |
 |
| ばんざい! | ヤゴ見つけた! |
同校ビオトープは、平成一四年三月、(財)日本生態系協会主催の「第二回全国学校ビオトープコンクール」において優秀賞を受賞しました。三〇〇件の応募問い合わせの中から、一次(書類審査)二次(現地審査)に進み、さらにその中から選ばれた一二校が最終審査(発表会)に臨みました。立待小はその中で見事、優秀賞を受賞しました。
審査内容は、ビオトープの質、児童生徒・地域住民・行政・環境NGOの参加・連携、教材としての利用、ビオトープの持続、地域への発展の可能性、等々です。特に立待小の場合、審査の中で「法定計画に基づく学校ビオトープの創設」ということが評価されました。
○法定計画による創設
つまり、鯖江市環境基本条例・同基本計画に基づき、議会で承認された予算により創設されたことに価値があるとの評価です。言い換えれば、個人的資金(寄付、会費等)でない、市民の税金が学校ビオトープに使用されたことの評価です。創設費用全額を税金で負担されたということは全国でもほとんどないということです。
 |
| 観察 |
○私たちの本音
私たちはみな、自然環境を大事に思っているつもりです。しかし、私たちはその事に自分の払った税金をどれだけ使えばよいか、ということになると話はガラリと変わります。
私たちの総意は行政予算の全体に対する自然環境保全予算の極小な割合をみればわかります。それは本音であり、私たちの自然環境の重要性に対する認識の実体です。まだまだ理解が足りないと言えましょう。
○学校ビオトープの価値と期待
学校ビオトープは、子供たちに自然を守り育てる体験を提供することで、「自ら環境問題を解決してゆく人材を育成すること」に大いに役立ちます。
さらに、地域の自然の恒久的拠点となり、これをネットワーク化することで、自然環境の質をより高めてゆくことが可能です。今後の発展に期待したいものです。
(ビオトープ管理士 井上 哲夫)
●ふるさとの環境自慢募集中!!
皆さんの故郷自慢で一ページを飾りませんか。千字程度の原稿に地図・写真を添付して応募してください。場所の紹介だけでも結構です。
採用された方には記念品をお送りします。
 |
| 狐川 |
◇これからの公共工事にもとめられれる役割―ものの豊かさの実現からこころの豊かさの実現へ―
終戦後からこれまで、公共工事は不足した道路や河川・公園などの社会資本を能率的に充足すること、いわばものの豊かさをいち早く実現し一定の生活水準を確保するために進められてきました。そして私たちは、安全で便利な生活を手に入れることができました。
一方で、それぞれのまちで長年維持されてきた生活様式や植物・動物が少なからず失われ、その結果、例えば子供たちの身近な野外の遊び場を奪ってきたことは否定できません。
この現状に加えて、既に高齢社会であり、今後人口減少をむかえる福井県において、これからの公共工事では、これまでつくってきた多くの社会資本を大事に使い長持ちするようにすること、そして地域らしさを守り、取り戻すことが必要であると考えます。
つまり、将来世代へこれまでつくったものをきちんと引き継ぐこと、そして人も含めた地域の生態系を保全・復元する公共工事が求められていると考えます。
特に、地域の生態系の保全・復元は、コンクリ―ト構造物のように放置しておくと時間の経過と共に価値が減っていくものではなく、いわば時間の経過と共に価値が増してくる可能性のある「公共工事」であると考えます。
また、そのために、進める過程においては、行政・建設技術者だけでなく地元住民や生物の専門家と協力して進めることで、こころの豊かさを実現できる公共工事が可能になると考えます。
そして、その中で緑化の果たす役割は、とても重要になります。
このような観点から、以下にこれまでの緑化とこれからの緑化のあり方を考えてみます。
◇緑化のこれまでとこれから
1.公共工事の緑化の現状と課題
市街地の歩道や中央分離帯に植えられた街路樹、道路沿いや公園の斜面に植えられた草や樹木(「法面緑化」といいます)など多くの公共施設に付随して植物が利用されています。このように緑化は、公共施設において欠かすことのできない重要な「脇役」といえます。
また、街路樹の役割は景観向上や大気浄化などがあり、法面緑化は土砂の侵食防止による安全の確保や自然環境の保全がその役割とされています。
 |
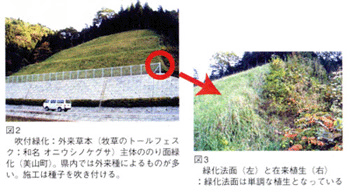 |
| 図1 プラタナスの街路樹(福井市) 県内の約6割の街路樹が外来種 |
しかしながら、これまで地域本来の種でない外国産の植物が多く用いられてきました(図1、2)。この結果、法面においては、なかなか本来の植生が回復しないといった問題も指摘されています1)。さらにこのような緑化した場所だけの問題でなく、周辺への影響も指摘されています。例えば、法面緑化に用いた牧草の種子が流れ出て河原で生育したり、山地部での砂防工事などで緑化に用いられたニセアカシア(北米原産の落葉高木)が河川に侵入したりすることは、よく知られており、本県でも真名川下流部(大野市)でニセアカシアをみることができます。
また外国産樹木が、植栽された場所から鳥による種子散布によって在来の森林群落内に侵入し、定着していることは、意外に知られていないようですが、近年、その保全が重要視されている里山(クヌギやコナラなどの雑木林)への侵入も稀ではないそうです2)。
このような、緑化における外来種の利用は、地域本来の生態系を根底から変化させる危険をはらんでいるため、できる限り止める必要があります。
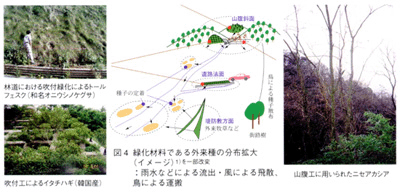 |
加えて、植物だけなくこれまで緑化に利用されてきた材料(土壌改良材や肥料)も、そのほとんどが県外や外国産のものであるため、今後は、資源の地域内循環や地場産業への貢献といった観点から県内産の材料の利用・生産の促進をすべきと考えます。
このように、緑化の課題は、「地域の生態系保全」と「材料の地域内循環」の実現であるといえます。
そこで、以下にこれらの課題を解決するための提案と方法を述べます。
2.緑化課題の解決にむけての方策
a.地域にあった緑化目標の設定―潜在自然植生の考え方の活用―
外来種の利用はいうまでもありませんが、地域にふさわしい、地域の生態系にあった緑化とは、どのようにして行えばいいのでしょうか。
その答えを教えてくれる一つの方法として、「潜在自然植生」の考え方の活用があります3)。「潜在自然植生」とは、植物生態学にある考え方で「現在ある場所で人間の活動を全て取り除いたときに、理論上、最後に成立する植生」のことで、現地周辺の植生調査に基づき、推定します。また、これから植生が移り変わる途中で出現する植生も決まります(図5)。県内でも潜在自然植生の考え方に基づき緑化の目標設定を行った事例がいくつかあります(図6、7、8、9)。
|
 |
図5 潜在自然植生の考え方により推定した、福井市運動公園1丁目における植生の遷移(移り変り)。ここでは、これをもとに緑化目標の設定を行った。 | |||||||||
| 【遷移現象の概念図】 | |||||||||||
 |
 |
||
| 図6 潜在自然植生の考え方の 活用による緑化 |
 |
図7 潜在自然植生による緑化 上段:宮崎村江波 下段:勝山市浄土寺 |
 |
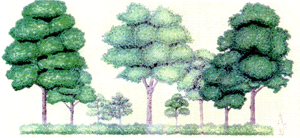 |
|
| 図8 吹付緑化でのススキ群落の形成 (手前がススキ、奥は、外来草本) |
図9 街路樹における潜在自然植生の考え方の活用事例 (福井市 フェニックス通り裁判所前、現在、住民参加により計画検討中) 現状のプラタナスの街路樹を電線地中化事業にあわせて土地本来の樹種にかえる予定。図の高木は、左からシラカシ、ケヤキ、タブノキで、その下にヤブツバキ、ウメモドキ、ダンコウバイ、ソヨゴなどを植栽。 |
このように、潜在自然植生の考え方を活用することで、それぞれの土地本来の具体的な植生を緑化目標にすることが可能になります。今後これを緑化における目標設定の方法として定着すべきと考えます。
b.材料の地域内循環―表土と発生木材の利用―
現状では、緑化の材料の多くは、県外産や外国産のものが用いられています。しかし、今後は県内の持続的に自立できるまちをつくるためのみならず、世界的な視点からも環境保全のために資源の地域内循環は、欠かせません。そのために、すぐ行うべきこととして、「表土」の利用と道路工事などにより伐採される木材や間伐材、街路樹の剪定枝などの「発生木材」の利用があります。
「表土」は、土壌の一番上の風化土と有機物からなる層(約30㎝)のことで、黒土とも呼ばれています。表土は構造物のためには、充分な強度をもちあわせていないことからこれまで公共工事では処分されてきました。
しかし表土には、隙間が多く、種子をはじめたくさんの有機物を含んでいるだけでなく、ミミズなどの生き物や土壌微生物も数多くすみ、植物の生育に適した栄養分をも蓄えています。また、表土は落葉などが分解されてできたもので1㎝の厚さができるのに100年かかるともいわれています4)。したがって、このように貴重な表土を保存し緑化のための材料に利用することは必ず行うべき最も基本的なことであるといえます。
「発生木材」の利用も今後一層積極的に進めなければならない課題です。道路工事などにより伐採される樹木や間伐材は、根株の移植や柵、マルチング(木材をチップ化し防草・保温・保水などのために植栽地に10㎝程度の厚みで敷くこと)、吹付緑化の土壌改良材の一部として利用することができます(図10、11)。
 |
 |
|
| 図10 根株移植と樹木チップによるマルチング 工事で発生した樹木の根を盛土表面に移植、 先端から芽が出てきている (国道27号バイパス美浜町佐田) |
図11 表土と樹木チップの吹付緑化 (福井市中野町、H14年11月施工) |
今後、このような現場ですぐに取り組めることを公共工事の関係者が共通認識を持ち、確実に進めることで資源の地域内循環が根づき、ひいては、福井県が持続的に自立できることにつながっていくものと考えます。また、種子や苗の県内での自給体制の整備についても重要な課題であり、これから一つ一つできることから実現していくべきです。
◇緑化の新たな役割―住民参加の緑化から住民の主体的なまちづくりへ
現在、持続的に自立可能なまちをつくるため、地方分権の徹底や地域の独自性の回復が重要になってきています。これを実践するためには、まちの歴史を学び、伝統を理解しなければならないことはいうまでありません。その意味から住民・行政・専門家が連携し、それぞれの知恵や知識を持ちよって、これからのまちを考え、行動していく必要があります。
そこで緑化は、この連携をつくるきっかけになる身近な取組であると考えます。自分達のまちの土地本来の植物を知り、みんなで汗して植えることから連携が生まれ、大人たちは自分の子供の頃を思い出し、子供たちは野外の楽しさと意外性を知り、そこから自分たちのまちを考える意識が生まれ、行動が始まるものと信じます(図12、13)。
 |
 |
|
 |
図13 小学生による植栽 (狐川、福井市運動公園1丁目) |
|
| 図12 住民参加の植栽 (金津トリムパークかなづ) |
緑化は将来世代に残すべきまちをつくり、心の豊かさを実現するための公共工事における大切な「仕事」であることを関係者全てが肝に命じなければならないと考えます.。
(福井県雪対策・建設技術研究所 研究員 坂田正宏)
引用文献
1)中野泰雄:緑の斜面づくりへの取り組み、日経コンストラクション2003年2月28日号、日経BP社p.104(2003)
2)日本生態学会 編集、監修 村上興正・鷲谷いづみ:外来種ハンドブック、㈱地人書館、p.48(2003)
3)(社)地盤工学会編:生態系読本 暮らしと緑の環境学、p.21(2002)
4)日本生態系保護協会編:日本を救う「最後の選択」、情報センター出版局、(1993)
井上 哲夫
(鯖江市糺町コミュニティセンター・設立十周年記念 実行委員長)
鯖江市糺(ただす)町の自治会(以下糺区)の「ごみなしイベント」について報告します。
糺区は本村区域、新興住宅街、マンション等合わせて約四百戸という大きな組織です。そこで昨年十一月、糺区の公民館である糺コミュニティセンター設立十周年記念事業が開催されました。記念式典、設立十年記念誌発行、記念イベント等、全区民が協力して盛大に開催されました。
 |
| ごみなしイベント |
○イベントは企画から
「何をするか」という企画委員会、その後、「それをいかにするか」という実行委員会をそれぞれ数回ずつ開催しました。
「何をするか」にいては、全体の趣旨として、
・十周年という節目で糺区まちづくりを振り返る。
・イベントを通じて未来へのまちづくりを糺区内外に発信する。
ということが委員会で決まりました。さらに未来へのまちづくりにおいて「環境」のキーワードをこのイベントでどのように表現出来るかを話し合いました。
その中で、「ごみなしイベント」の案が出ました。"ごみを出さないイベントこそ糺区の未来へのまちづくりの第一歩だ"ということからです。
○ごみなしイベントとは?
イベントごみのほとんどは飲食物に関するもので、使い捨て食器が広く利用されています。しかしその結果、残るものはごみの山なのです。
そこで、いかに「ごみなしイベント」をやり遂げるかについて話し合い、
・実行委員会が頑張っても、参加者の協力がなければなしえない。
・ごみなしは参加者一人当たりの負担にすれば小さなものである。
さらに
・参加者に自分の食器を持ってきてもらおう。
・使った食器は各自が会場で洗ってもらおう。
・「エコパック」なるものを記念品として全戸配布して、これに自分の茶わん、コップ、皿、ハシ、ふきん、ナイロン袋を入れて持ってきてもらおう。
ということになりました。
 |
| エコパック |
○趣旨の告知
成功させる手段として、区民広報誌や「エコパック」の事前配布、マスコミ等の利用などを積極的に行いました。ある新聞社は、「『買い物袋持参運動』という話はあちこちで聞くが、『エコパック』によるマイカップ持参運動というのは聞いたことがない。興味深い。」といって、事前に大々的に報道してくれました。
○誰が成功させたか?
結果、これといったトラブルもなく、この企画は区民の理解と協力をもって成功しました。私はこのイベントの実行委員長でした。その日は、実行委員長として鼻高らかに反省会で酒をのみました。・・・しかし。
よく考えれば、もともと四百戸の参加区民の協力が得なければ出来なかったことなのです。なぜ協力が得られたのか・・・実行委員長が良い人だったから?・・・とんでもないです。それは区民一人一人の心の中に「環境」に関する芽生えが備わっていたからなのです。今や誰しもが行動に表さなくとも、心の中では思っている時代なのです。
委員会はそのきっかけづくりをやっただけなのです。
○みんなでやろう!ごみなしイべント
今年も春から各地でイベントが繰り広げられます。主催者のみなさん、「ごみなしイベント」の企画をたて、参加者には協力してもらいましょう。きっとうまくいきますよ。私たちの住む糺区でも出来たのですから…。
| 読者の窓 |
(春江町 主婦)
(吉田郡 パート 女)
(丹生郡 会社員 男)
(敦賀市 無職 女)
(勝山市 無職 女)
 |
| 基調講演 |
去る三月十五日(土)、福井県国際交流会館において、『ふくい環境シンポジウム』を開催しました。
基調講演では、夫婦漫才師の林家ライス・カレー子さんを講師に迎え、「笑いの中で考える循環型社会」をテーマに、「思いは地球規模で行動は足元から」のスローガンのもと、身近なデータと笑いと実践を盛り込んだ話が展開されました。二一世紀のキーワードは「もったいない」、モットーは「明るく 元気で 一生懸命」とわかりやすく、ユーモアたっぷりの語りで会場をわかせました。
パネルディスカッションでは、コーディネーターに仁愛大学人間学部の加藤隆夫教授、パネリストには福井日本電気株式会社社長の高橋昌之氏、福井県連合婦人会会長の河原はつ子氏、池田町環境向上推進室係長の溝口淳氏に林家ライス・カレー子さんを加え、会場を交えた活発な討論が繰り広げられました。
まず高橋氏からは、企業代表の意見として、現在はデザインや価格よりも、環境に配慮された商品が求められていること、また、会社の取組みとしてグリーン購入やゼロエミッションの達成などが紹介されました。
河原氏は消費者代表として、「リサイクルやごみの分別は作業が面倒だが、行動を支えるのは自分たちの意識。環境問題の啓発、また、次世代のためには環境教育が大切。これからは商品を作る側の企業も巻き込まなくてはならない時代。」と述べられました。
溝口氏は行政代表として、「池田町は、家庭の台所から出る生ごみを回収し、町の施設で牛糞、籾殻を混ぜて堆肥作り、それを利用して作った作物を地域やアンテナショップで販売している。行政として、町民に意識を持ってもらえる企画や仕組みを思案中だ。」と述べられました。
 |
| パネルディスカッション |
そして、加藤教授は、「県民全体がもっと環境に興味を持ってほしい。そのためには啓発、啓蒙がもっと必要であると感じた。」と述べられました。
会場からは、「商品として売り出す前に、企業として環境配慮されていないものは規制すべき。」、「外国からたくさん安い商品が輸入されている中で、グリーン商品の販売、企業への助成等が必要」、「商品が故障したら、修理するより新品を購入した方が安いという現実がごみの増加につながっているのではないか」など、実情に基づく多彩な質問が挙げられました。
最後に、加藤教授は「英知を集結して、恵み豊かな福井の環境を将来もずっと子孫に残していくことが、私達の責務だと思っている。ぜひ一人ひとり努力してほしい。」とまとめられました。
今回のシンポジウムでは、様々な立場から、実践に基づいた報告や意見、質問などが熱心に論議され、交流が深まったと共に、循環型社会のために私達自身、身近なところで何ができるかを考えるきっかけとなったのではないでしょうか。
地球温暖化は私達の日常生活や通常の事業活動に伴い排出される二酸化炭素等の温室効果ガスの増加が原因となっています。
県と関西広域連携協議会では、オフィスからの温室効果ガス排出量の削減を目指す「エコオフィス宣言」運動を推進し、賛同する事業所を募集します。
1 募集期間
平成15年4月1日(火)~5月30日(金) (その後も適宜受け付けます)
2 宣言事業所の要件
(1)次の取組みの中から2項目以上を選択する。
〔節電等〕 ①冷房28℃以上&軽装勤務
(夏のエコスタイル)
②冷房28℃以上 ③暖房20℃以下
④不必要な電灯の消灯
⑤OA機器等の不要時電源OFF
〔省エネ〕 ⑥省エネ型機器の購入
⑦断熱材等省エネ設備導入
⑧太陽光発電等新エネ設備導入
⑨節水
〔交通等〕 ⑩アイドリングストップの推進
⑪公共交通機関利用奨励
⑫ノーマイカーデーへの参加
⑬自転車通勤奨励
〔その他〕 ⑭屋上緑化 ⑮敷地内緑化
⑯グリーン製品の購入
⑰ごみ分別の徹底(ごみ箱の削減)
⑱その他(独自の取組み)
(2)年度末に取組み実績を県に報告する。
3 申込み先
福井県福祉環境部環境政策課
〒910-8580 福井市大手3丁目17‐1
電話 0776‐20‐0303
FAX 0776‐20‐0634
E-mail : kankyou@ain.pref.fukui.jp
・新聞、県のホームページ等に宣言事業所名を掲載します。
・宣言ステッカーを配布します。
県では、環境問題に関する学習会等を、活動団体や公民館、地域のグループなどが開催する場合、講師として環境アドバイザーを派遣しています。
現在、環境汚染・自然環境・地域活動・エコライフなど7つの分野に、23名の環境アドバイザーが登録されています。派遣は年20回程度を予定しており、予算の範囲内において、派遣に対する謝金および交通費を負担します。
派遣を希望される方や詳細を知りたい方は、県環境政策課まで御連絡ください。
また、福井県環境政策課ホームページ
(http://www.pref.fukui.jp/kankyo/index.html)
でも、アドバイザーの名簿など詳細を掲載しておりますので御覧ください。
問合せ先:福井県福祉環境部環境政策課 TEL0776-20-0301
「私たちの活動紹介」に応募してみませんか?
500字程度の原稿に、写真を添付してください。採用された方には、記念品をお送りいたします。
詳しくは、環境ふくい推進協議会事務局までお問い合わせください。(TEL 0776-20-0301)
環境ふくい推進協議会では、随時会員を募集しています。
環境問題に関心のある方、本紙「みんなのかんきょう」を毎号読みたい方、当協議会主催行事等の情報を知りたい方は、ぜひ御入会ください。お待ちしております!
《年会費》
個人会員:500円
企業会員:10,000円(1口以上何口でも可)
団体会員:無料
《申込み・問合せ先》
環境ふくい推進協議会事務局(福井県環境政策課内)
Tel.0776-20-0301
| 編 集 後 記 |
世界水フォーラムが開催され、ますます水環境が注目されています。 我が家では、トイレのタンクに節水コマをつけたり、洗い物をするときは、あらかじめ余分な汚れを新聞紙などで拭き取るなど、一般家庭でもできることから実践しています。 環境を守るためにはやはり一人一人の意識が大切だと思います。 (S) |