みんなのかんきょう |
第27号 平成13年8月発行
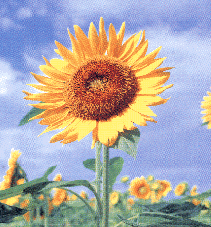 |
|
(撮影/青木 誠)
みんなのかんきょう |
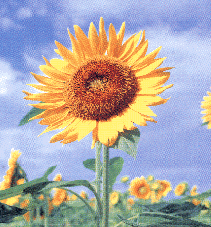 |
|
ふるさとの環境自慢
(武生市蓬莱町) 「蔵の辻」
JR武生駅から、西へまっすぐに5分ばかり歩くと、左手に蔵が現れる。白壁の真新しい蔵のまちなみだ。
武生市の中心部にある、20棟ほどの蔵が建ち並ぶ蓬莱地区のこの一角は、『蔵の辻』と呼ばれている。
江戸時代に、禁令や犯罪人の罪状を記す幕府の高札を掲げた「札の辻」を中心に、情報交換のため人が集まり、周囲が栄え、この辺りに商家が連立するようになったという。
以降、武生の商業の中心として栄えた蓬莱地区には、物資の中継基地として商品を保管しておくための土蔵がいくつも建てられた。しかし時代が移り、中心市街地の商業が活気を失うとともに、蔵も次第に使われることがなくなっていった。
こうした趨勢と市街地再開発のため、古くから残る蓬莱地区の蔵も取り壊される予定だった。しかし、この蔵を生かしたまちづくりをしていこうと、地元の商店街や市役所が一丸となって取り組み、蔵の外装をそのままに残すこととなった。
そして、現在の商家の蔵を中心とした景観が整備された。
武生は、歴史の古い町である。市街地は古くは府中と呼ばれていた。『府中』というのは古代律令制の時代に国府が置かれていたことを示す地名であり、今でも『府中』や『国府』といった町名が残っている。
国府が置かれていた証拠として、蓬莱町の隣の京町には、今でも総社大神宮や国分寺がある。この辺りには、寺社が多く建ち並んでおり、お寺巡りをして歴史探索をするのもまた一興である。
また、平安時代には、『源氏物語』の作者 紫式部が、父親が越前守として、当時越前の国府であった武生に赴任した際に、1年数ヶ月ではあるが、京の都から居を移していたとのこと。
江戸時代になってからは、政治・経済の中心は福井へと移ったが、北陸街道の宿場町として栄え、当時は、南北に、防火や除雪、飲用など多目的に利用された用水が流れていた。今では桂町に、その用水が一部だけ残されている。
こうした昔ながらの風情が残っているところで、昔の人々の暮らしに思いを馳せてみると、この暑さも少しは和らいで感じられるだろうか。
★ふるさとの環境自慢募集中!!★
皆さんの故郷自慢で一ページを飾りませんか。
1,000字程度の原稿に地図・写真を添付して応募してください。場所の紹介だけでも結構です。
採用された方には記念品をお送りします。
JR武生駅から約400メートル、徒歩約5分
これからの環境を考える講演会
『環境の世紀を目指して』
去る7月24日(火)、福岡大学法学部長 浅野直人氏(中央環境審議会委員)による講演会が県主催で開催されたので、その概要をご紹介します。
地球温暖化については、ボンでのCOP6がようやく合意に達し、日本の二酸化炭素(CO2)森林吸収分3.7%が認められることになりました。しかし、99年のCO2排出量は90年に比べて既に6.8%増えており、90年レベルから6%削減するためには単純計算で12.8%削減する必要があります。つまり、森林吸収で認められた3.7%を差し引いても、9%下げる必要がありますが、京都議定書締結後もCO2排出量は削減されていません。
さて、かつての公害問題は、我々は被害者で企業側が加害者という構図でした。1967年に公害対策基本法ができてから、急速に対策が進み、産業公害はかなり解決を見たのですが、自動車交通公害や家庭からの雑排水、増える一方のごみ、これらが大きな問題となるとともに、身の回りの自然が徐々に失われてきました。
リオで地球サミットが行われた年(1992年)あたりから、公害対策と自然保護というこれまでの環境政策を見直す動きが出てきて、環境基本法が制定されることとなりました。環境基本法の本質を一言で表すと、「環境への負荷の低減」ということです。人類が生き延びるためには環境への負荷をできるだけ減らして、生き物と折り合いよく暮らしていくことが必要です。環境基本法は環境への負荷を最小限にしていくために努力しましょうという法律で、これに基づいて作られたのが環境基本計画です。
1994年に作られた環境基本計画では、「循環、共生、参加、国際」をキーワードとして、基本計画の中心をなす長期的目標で使われています。
環境基本計画における『循環』とは、もともと自然の中では物質の循環がうまくバランスがとれていたものが、どこかの段階で人為的にかく乱されて変わっていくことが問題だということです。我々の生活は便利さを追求するあまり、本来の循環の姿からは離れてしまったのですが、それをできるだけあるべき循環の形に近づけていこうというのが、環境基本計画の『循環』の意味です。
一方、環境基本計画ができた1994年以降、わずか8年の間にわが国の環境政策には大きな変化がありました。
昨年12月に改定された新環境基本計画では、環境基本計画の進捗状況の点検の結果を受けて、重点的に取り上げる項目を精査しました。11の項目で構成される戦略プログラムのうち、分野別の6つの項目(注)はこれまで十分に取り上げてこなかった、あるいは取り上げてきたが成果をあげてこなかったという項目で、これから考えなければならない課題が山のようにあります。これらの課題が持っている共通点にしっかりと目を向ける必要があり、誰かが加害者でこちらが被害者であるという捉え方では解決できない問題といえます。
CO2排出のシミュレーション結果によると、都心よりも地方の自動車による排出量が増加することが問題だと言う人がいます。都心は公共交通機関が発達していますが、地方の人が自動車に乗るのをやめろといわれたらどうなるのでしょうか。一家に2台自動車を持たざるをえないのは交通弱者です。それをきちんと意識したうえで、日本全体の政策を考えなければいけません。
では、地域の環境政策には何が求められているのでしょうか。分権型社会がそのキーワードです。分権といっても、自分のところだけがよければいいと考えることではありません。お互いに話し合ってシェアをし、役割分担をして地域を作っていくのです。分権は自己決定、自己責任といわれますが、同時に最終目的としては共に生きるということです。これはそのまま環境本位の地域づくりにつながります。
現在及び将来の世代の人間に、健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受させること、人類存在の基盤である環境を将来にわたって維持すること、これがわが国の究極の環境政策の目標です。これを具体的に実現するために、地球全体のことを考えて持続的発展が可能な社会を形成していく必要があるのです。
先人が残してくれた恵みを次の世代に残していくことを通じて、私たちは時間を超えて共に生きていることになります。つまり時間軸を超えた人との共生、それと同時に地域軸を超えた人との共生ということが大事な要素なのです。
(注)
・地球温暖化対策の推進
・物質循環の確保と循環型社会の形成に向けた取組
・環境への負荷の少ない交通に向けた取組
・環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組
・化学物質対策の推進
・生物多様性の保全のための取組
特 集
環境学習を考える
学校での総合的な学習の時間や地域の学習講座などで、このところ『環境』がよく取り上げられ、『環境学習』に対する関心が高まってきている。この背景にはいったい何があるのか、そして環境学習は我々に何をもたらすのかを考えてみたい。
◆環境学習の必要性
『環境学習』、『環境教育』という言葉を耳にする機会が増えているが、いったいどういう意味なのだろうか。
子供の頃を振り返ってみると、学校の理科の時間に化学的な実験をしたり、生物のことを学んだり、社会の時間には大都市の公害やごみ処理のことを勉強したが、それらはあくまで『理科』・『社会』という教科の枠の中であった。環境問題と関連付けて学んだ覚えも、自分の生活と結びつけて考えたこともなかった。当時は、身近に自然があふれるほどあり、消費することが豊かさの象徴のような時代であった。
こうした大量生産・大量消費・大量廃棄の経済システムが、今日の環境問題を引き起こす原因となったことは、これまでにも本紙上で述べている。現在の環境問題の多くは、我々の日常生活に原因があり、これを解決するためには、わたしたちの日常生活を環境への負荷の少ないものに変えていく必要があるということは、既に周知のことと思う。
『環境学習』、『環境教育』は、「人間と環境との関わりについての正しい認識にたち、自らの責任ある行動を持って、持続可能な社会の創造に主体的に参画できる人の育成を目指すもの」(中央環境審議会報告書「これからの環境教育・環境学習」)であり、まさに今日的課題ということができる。
◆地域に根ざした取組み
公害や自然保護などについては、以前から進められていたが、日本で環境学習としての取組みが広がり始めたのは、1980年代後半からである。
県では、平成2年3月に『福井県環境教育基本方針』を策定した。これを受けて、平成2年度に環境教育用教材としてビデオを作成、そして平成3年度から11年度までは、ゆとりの時間や自由研究、体験学習等の中で活用できるようにと、毎年、小学校5年生を対象とした環境教育副読本を作成。平成4年度からは、小・中学生が自分たちの身の回りの環境の中からテーマを見つけ出し、そのテーマについて自主的に調査研究することを支援するための「地域環境ジュニアパトロール」(本紙第22号特集で紹介)事業を実施してきた。
また、平成6年度からは、地域や団体などが主催する環境学習会などに、アドバイザーとして専門家を派遣したり、紹介したりする制度を設けている。
さらに、自然保護センターや平成11年に完成した海浜自然センターなどでも、身近な自然環境を考えるためのプログラムが積極的に行われている。
一方、市町村においても、鯖江市や武生市などでは、環境教育のリーダーの養成や環境問題への関心を深めてもらうための市民講座を開催しているほか、公民館でも地域内の環境保全のため講座を開講したり、学習プログラムを組んだりしている。
また、当協議会などの環境保全団体では、自発的な活動の推進母体として、地域に根ざした様々な活動に取り組んでいる。
当協議会の事業である親子環境教室では、夏休み期間中に小学生を中心とした親子を対象に、リサイクルやエネルギーなど、毎年テーマを変えながら、できるだけ子供たち自身の体験を通して、環境問題を学んでもらっている。
昨年度からは新たに、ふくいエコ・カレッジを開催している。これは、地域における環境保全活動等の中心となる人材の育成を目的に、ディスカッションを通して、受講者に一歩進んだ環境に関する意識および知識を得てもらおうというものである。
一方、丹南地域環境研究会では、自治体主催の環境学習講座に参加するだけではなく、独自に地域の環境に関する学習や調査を行い、行政への政策提言やビオトープづくりを実践するまでに活動範囲を広げている。
このほかにも、子供から大人まで幅広い世代を対象に自然体験の企画などを行ったり、様々な活動をしている団体が数多くあるが、紹介はまたの機会としたい。
◆学校での取組み
福井市の社西小学校では、平成14年度から本格的に始まる「総合的な学習の時間」のモデル校の指定をうけ、『環境教育』を実践している。
そのプロセスは、まず、自分たちがどんなことをしたいかを子供たち自身が話し合って、自分たちの地域を調べることを決める。そして、自分たちの地域の問題を見つけ出し、地域を流れる狐川を中心に実地調査や実験などの体験を通して、また、外部から招いた講師の話を通して、さらに、自分たち自身で図書館やインターネットで調べることを通して、問題への理解を深めた。そして、その解決のために何が必要か、自分たちなりの結論を導き出し、解決に向けた実践行動にまで結び付けていっている。
このように学校というフィールドの中においても、以前のような決められた教科の一部としての学習ではなく、『環境』というものをひとつの教材として捉えた学習が始まっている。
そして、社西小学校では、これを学校の中だけでなく、公民館を中心とした地域へと、そしてさらに市の環境基本計画策定市民の会への提案へとつなげている。
子ども環境会議
◆環境学習へのバックアップ
学校や地域において環境学習への取組みが盛んになってきている一方で、環境学習に取り組みたいと考えているが、自分たちでどのようなことができるのか、どのような方法で取り組めばいいのか、どこへ何を聞いたらいいのか、どこに必要な情報があるのかといったことがわからないという声が聞かれる。
そこで、県では、こうした要望に応えようと、平成12年度に『環境学習ガイドブック』を作成した。
ガイドブックでは、地域や学校で環境学習を進める際に、指導者の手引書になるようにと、環境学習へのアプローチ手法やプログラムなど、指導の参考となる情報から、環境学習施設、環境情報の検索先、環境学習の事例やマニュアル等に関する書籍など、環境学習に必要と思われる幅広い情報を紹介している。
しかし、これらがどのように使われているのか、また、現場の指導者が使用していく上での問題点などのフォーローアップは十分とはいいがたい。環境学習の輪を広げていくためには、行政と学校や地域・団体などの環境学習の現場が、より連携を深めていく必要があるのではなかろうか。
また、広域的な取組みとして、福井・滋賀・三重の3県の子供たちが集まり、環境問題について考え、意見交換を行う「子ども環境会議」が平成11年度から始まり、昨年は本県の奥越の地で開催された。
今年は3県に岐阜県を加えた4県の子どもたちが、この8月、三重県に集まり、環境問題について話し合い、その結果を発表しあった。
いろいろな地域の子どもたちとの意見交換により、自分たちが普段考えなかった問題に気付き、環境問題をさらに深く捉えていくきっかけとなった。
しかし、環境学習の機会や情報を提供することが、最も重要なのではない。
数多くの人々がこうした場に参加し、環境問題に関心を持ち、認識を深め、そして、具体的な行動につなげていかなければ、私たちが直面している環境問題は、何一つ解決しない。
専門的な知識や技術、ツールなどが必要な環境学習もあるだろうが、家庭での省エネやごみの分別などは、日常生活の中で簡単にでき、なおかつ、最も基本的で重要な環境教育である。
こうした身近な環境学習・環境教育の中にこそ、環境問題を解決していく糸口があるのだと思う。
グリーン購入ふくいネットの概要
【会 員】県、市町村(35)、企業(233)、
団体(21) (平成13年7月末現在)
【事務局】福井県福祉環境部環境政策課
電話0776-20-0301
【幹事会】事業内容を企画・検討する機関
【申込み】事務局に入会申込書を郵送・FAX、
または、ホームページから申し込めます。
(http://info.pref.fukui.jp/kankyou/index.html)
【会 費】無料「グリーン購入ふくいネット」の設立
前号の特集で紹介したように、持続的発展が可能な循環型社会を構築していく上で、「グリーン購入」(物品やサービスの購入に際して、必要性を十分考慮するとともに、環境への負荷の少ないものを優先的に選択すること)は、極めて重要な取組みです。
福井県内において、グリーン購入の取組みの輪を広げるため、去る7月10日、行政・企業・団体で構成する「グリーン購入ふくいネット」が設立され、併せて、設立記念フォーラムが開催されました。
フォーラムでは、「循環型社会の構築に向けて、グリーン購入の意義」と題し、武蔵工業大学の中原教授の基調講演がありました。
大量廃棄社会への警鐘、グリーン購入の動向、環境配慮表示の問題など、グリーン購入推進のスタートにふさわしい興味深い内容で、講演後、グリーン購入ネットワーク(GPN)の活動、福井県庁および清川メッキ工業㈱の取組み事例が紹介されました。
ふくいネットでは、今後、ホームページによるグリーン商品や販売店等の情報発信、情報紙の発行、ブロック別懇談会による会員間の連携などを行っていきます。
随時、入会の受付を行っていますので、グリーン購入に関心のある企業・団体は、ぜひお申込みください。
読者の窓
●これからの商品購入は、『グリーン購入に参加している企業』の商品を、消費者は買っていくでしょう。商品選択の大きな基準となるでしょう。 (鯖江市 主婦 女)
●「グリーン購入の取組み」の記事は、時宜を得た企画と思いながら読みました。滋賀県だけでなく、全国的に適切に早くすべきと思います。当県での取組みを期待しています。 (大野市 無職 女)
●これからの社会は、世界人口の増加による資源不足とごみの増加、汚染物・有害物質の増加など、多くの問題をかかえています。循環型社会の形成は、こうした社会の中で焦眉之急であることを知らされました。1年でも早く進めたいものです。 (大野市 無職 男)
●「ふるさとの環境自慢」に、当地の鵜の瀬が掲載されており、うれしく思いました。 (小浜市 公務員 男)
●山内フミ子氏のエッセイ中、「大木や動植物が長い長い年月の間に化石となり…」の件を読んで、化石燃料とは太古の動植物が地球にしかけた時限爆弾で、人間がそのスイッチを入れてしまったとも言えるのかなと思いました.。 (武生市 主婦 女)
平成13年度 環境ふくい推進協議会総会の結果について
去る、5月24日(木)、福井県国際交流会館(福井市)において、平成13年度の環境ふくい推進協議会総会が開催されました。
まず、平成12年度事業および収支決算について事務局からの報告の後、監査委員から事業の執行および会計経理が適正に処理されているとの報告がありました。
また、平成13年度の事業の実施について、次のとおり決定しましたのでお知らせします。
【平成13年度事業計画】
一 環境保全活動促進事業
① ふくいエコ・カレッジの開催
(化学物質や環境学習等をテーマに4回開催)
② 環境教室の開催
(親子環境教室:夏頃、企業研修会:秋頃)
③ 環境アドバイザーの派遣助成(対象…企業会員)
④ 環境カレンダーの作成(平成14年用)
⑤ 環境美化活動の推進
(「クリーンアップふくい大作戦」の主唱)
⑥ 地球環境保全活動の推進
(「アイドリングストップ運動」および「ノーマイカーデー」の普及啓発)
⑦ リサイクルの推進
(「ごみスリム・スリム運動」と連携し、リサイクル活動を推進) 等
二 シンポジウム開催事業
県と共催で、14年2月に「環境シンポジウム」を開催
三 情報紙発行事業
「みんなのかんきょう」を年4回発行
四 表彰事業
環境保全活動に取り組んでいる個人、団体等を表彰
(今年度表彰者は、後記のとおり)
五 普及広報事業
パンフレットの配布やホームページの充実
平成13年度環境ふくい推進協議会
会長表彰受賞者名(敬称略)
●個人の部
五十嵐千恵子 折戸外二 木本湛子
●団体の部
朝日町婦人会 遅羽町住民協議会
福井市三世代連絡運営委員会 フルーツキャンディ
美浜町くらしの研究サークル
●学校の部
朝日町立朝日東中学校 河野村立河野小学校
福井市国見中学校 福井市酒生小学校
※ 各事業の実施時期および詳細については、
その都度情報紙やちらし等でお知らせします。
県では、地球温暖化防止対策の一環として、夏の間【6月21日(夏至)〜9月23日(秋分の日)】、庁舎内の冷房温度を適正冷房(28℃)に設定するとともに、適正冷房にふさわしい軽装での勤務を実践する、「夏のエコスタイル」を推進しています。
また、この趣旨に賛同する県内事業所、市町村、関係団体等においても、同様の取り組みをしています。
毎日暑い日がつづいて、電気などの使用量が増えがちですが、地球温暖化を防止するため、ご家庭でも、適正冷房の励行に努めるようお願いいたします。
福井県福祉環境部環境政策課 TEL 0776−20−0301
ごみ減量化・リサイクル日本一
推進県民大会2001
ごみ減量化・リサイクル日本一推進県民大会2001を、下記のとおり開催します。
多数の御参加をお待ちしております。
と き 平成13年9月8日(土) 13:00〜
ところ 福井県自治会館 2階 多目的ホール
(福井市西開発4丁目202−1)
内 容 ステージ
☆トークショー
テーマ:ふるさと自慢
地球にやさしい街づくり
講 師:ダニエル・カール 氏
☆リフォームファッションショー
展 示
☆リフォーム作品展
☆福井県認定リサイクル製品
福井県福祉環境部廃棄物対策課 TEL 0776−20−0317
環境カレンダーの写真を募集します! 環境ふくい推進協議会では、「平成14年環境カレンダー」に掲載するための、美しい自然環境の写真を募集します。採用された方には粗品を贈呈いたします。
御応募お待ちしております!
≪応募規定≫
・自作、未発表のものまたは発表予定のないもの
・大きさは、サービス版(8cm×12cm程度)からA4版までで横長のもの
・カラー撮影で、採用の際にネガの提供ができるもの
・3年以内に県内で撮影したもの(特に冬のもの)
・タイトル、氏名、住所、電話番号、撮影場所、撮影年月日を記入してください
≪締 切 日≫ 平成13年9月28日(金) 必着
≪結果通知≫ 応募者全員の方に、結果を通知します
≪作品の取扱い≫
応募作品は原則として返却しません。
また、採用作品の版権は、環境ふくい推進協議会に帰属します。
≪応 募 先≫ 〒910-8580 福井県環境政策課内
環境ふくい推進協議会事務局 TEL 0776‐20‐0301(直通)
編集
後記◇毎日暑い日が続いて、自分が亜熱帯に住んでいるような気がしてしまうほどですね。朝から日差しがきつくて、外出の際には帽子が手放せません。これも地球温暖化の影響でしょうか。そうだとしたら、少し怖い気がしますね。(E)