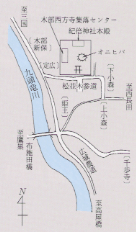●紀倍(キベ)神社のオニヒバ ・県指定天然記念物
樹 種 ヒノキ(ヒノキ科)
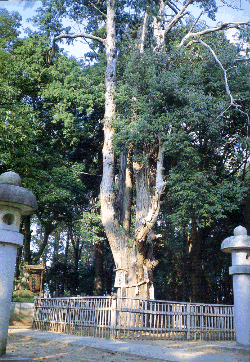
幹回り 3.7 m
樹 高 21 m
樹 齢 400年以上
所在地 坂井郡春江町木部西方寺
所有者 紀倍神社
紀倍(キベ)神社の鳥居から南に延びる松並木の参道は神社の直前で、定広か ら西長田に通ずる県道と交差している。鳥居脇の“オニヒバ由来記”によると、 大昔この辺りは湿地帯で、水鬼と呼ばれる怪物が出没して農民を困らせていた のを、水鬼討伐隊に比叡山の僧兵隊も加勢し退治したのが1200年程前の10月19 日である。水鬼を葬った塚に植えた檜(ヒノキ)(オニヒバ)は信長の異神仏焼 払いで焼失し、今境内の中央にある檜は焼跡に植えた二代目であると書かれて いた。
紀倍は鬼部または木部とも書かれる。檜の主幹は1本が普通であるが、この 樹は地上3 m位から4本に幹分かれして上に伸びている。葉の着きも少なく、 枝枯れが目立つ老木である。福井県には檜の巨木は少ない。
檜は古くから日本人の暮らしと深く結び付いた用材で、色艶も良く、強靭で 耐久性に富み、最良の建築材である。また、特有の木の香は人々に好まれて、 高級嗜好を満たしてくれる。檜材の用途は、建材以外にも多い。船舶、器具、 彫刻等広く使われる。また、樹皮は昔から檜皮葺(ヒワダブキ)として、社寺の 屋根を葺く材料にする。ヒノキの名は火の木からと言われ、昔は火種を檜の板 を摩擦して作った。檜は別称、ひ・ひば・さきぐさとも言う(広辞苑)
ちなみに私が紀倍神社のオニヒバを見に行った日が、10月19日、水鬼の命日 であった。
(文:写真 榎本二郎)